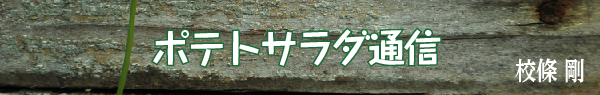ポテトサラダ通信 39
その果てを知らず
校條 剛
SF作家と呼ばれることの多い小説家、眉村卓さんが亡くなられたのは2019年の11月3日のことだから、この文章を執筆している時点で一年余り経っていることになる。
その一周忌を目前にして、講談社から一冊の単行本が届けられた。「謹呈 著者」のしおりが挟まれているが、著者は亡くなっているので、一人娘の村上知子さんのご厚意であった。
題名は『その果てを知らず』。読了後すぐには、このタイトルの意味は分からなかった。最後の34章、35章を再読してやっと、作者の意図が理解できたような気がしている。
作者は現実としての「死」を覚悟し、目測した時点で、「永遠の命」という「果ての知れぬ」概念について思いを深めようとしているのであった。主人公に対して、次のような言葉が投げかけられる。
<いよいよになってもあなたの生命力はつづくのです。もちろんそれはこの世界のこの宇宙ではなくて、われわれの宇宙と重なった別の宇宙ですがね。でも人間ではなくても別の生命体をつづけるのは確かです。>
本書のテーマの一つである「生命の永続性」は「またか」と言われるテーマかもしれないが、さすが練達の「不思議小説」の作家 眉村卓の描くイメージは独特で、しかも切羽詰まった意気込みを感じさせない。この作品の魅力の一つはメッセージを発しながら、読者を説得しようと力を籠めたりしていない点にある。
実は、本書のテーマよりも私に強く訴えたのは、リアルに描写されている「老い」の実際だった。観念的な「老い」ではなく、手で触れるように実際的な「老い」と「衰え」である。「老衰」とはよく言ったものだ。若い頃と違って、現在70歳の私には、10年後、20年後に我が身を見るような言葉がひどく沁みたのだ。
本作の主人公(作者その人であろう)「浦上映生」は、現在84歳。6年前に食道癌で大手術を受け、痩せこけたが元の生活に復帰した。だが、その4年後にリンパ節への転移があり、手術。誤嚥(ごえん)性肺炎に罹ったりしたが、なんとか乗り越え、今度は腫瘍の肥大によって入院している。もう年齢的に手術は難しいので、抗がん剤と放射線治療に特化して療養している。
そういう状態にある主人公が述べる「老衰」の描写や説明のなかで、最もリアルにこちらの胸に響いたのは、脚の筋肉が失われ、立ち上がるのさえ困難な「うどん足」になるという部分である。少し長いが、以下に引用してみよう。
<だからきょうも食べるものは自分で何とかしなければならない。ま、こういう生活をしているから、レトルト、乾燥食品など、数日分の貯えはあるが、やはり最終的には、立って、食べられるように仕上げる(?)わけで、その立つという行為がなかなか大変なのだ。右脚が妙に力抜けして、バランスが取れないのである。それが体内で進行している癌のせいなのか、医師から支給されている抗癌剤の副作用なのか、はっきりとはわからない。そして細くなった体は自由には動かないので、起き上がり体を立てるためには、布団の上で半回転したり腕、肱を使って身を起こそうとするけれども、それでたしかに体は動くけれども、立ち上がるのはなかなかの難事であった。足全体が柔らかくなりぐにゃぐにゃになって、まるきりうどんなのだ。体調があまり思わしくないときは、うどん化が進行しているのである。体の筋肉の大半が、長期にわたるたびたびの入院で、あらたか消失してしまったので、なかなか元に戻らない。いや、戻るかどうか怪しい。体を支え移動させてくれる足が、体のお荷物となってしまったのだ。頼りにならぬうどん足、油断をするとよろよろぺたんのうどん足人間であった。>
私は読みながら、おもわず自分の脚を触ってしまった。
本作では、眉村さんの、毅然たる姿勢にも思い至る。それは、長く連れ添った妻への言及がない点である。私生活を綴ったノンフィクションを主軸とした『妻に捧げた1778話』では、最後の最後の行で「また一緒に暮らしましょう」と述べて読者の感動を誘ったのだが、今回の純フィクションの小説では、妻は登場するものの、別世界へ旅立つときには、「別の生命体」になり、地球をはるか見下ろす雲のような存在に含まれて、個人的な履歴は消し去られる。当然「妻」という特別な存在とも永遠の別物として生きていくわけである。
感傷も悲哀もなく、ただ不思議な虚無感が流れる『その果てを知らず』。高齢者に是非読んでもらいたい。