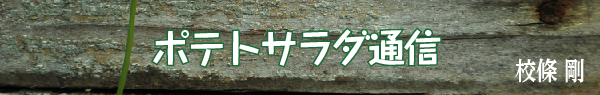ポテトサラダ通信 38
『富士日記』のこと
校條 剛
武田百合子の『富士日記』中公文庫全三冊を読んだ。新版なので文字が大きく、厚さも450ページ前後となかなかのボリュウムである。上下巻二冊が940円、中巻一冊が960円で合計2840円、税込みだと3124円になる。単行本一冊だと尻込みする値段であるが、なぜか文庫だと買ってしまう。
この日記は、武田泰淳・百合子夫妻が山梨県南都留郡鳴沢村字富士山の富士桜高原別荘に暮らしているときのみ記録されている。
百合子さんが、この日記を書くことになったのは、夫である作家武田泰淳の勧めによるもので、家計簿として、毎日の買い物の代金や、別荘のメンテ代など主に支出金とその内容をメモするのが目的だった。野菜や卵、肉などの食料品のほかに、ガソリン代、食事代、外構石積の工事代などおよそ別荘生活で支出した金額を細かく記録している。朝昼夜の食事の内容も漏らさず記入される。そういう個所は読むほうにとってみれば、だんだんとうるさく感じられるが、この目的がなければ、おそらく文筆家武田百合子は誕生していない。百合子はそもそも文章表現に積極的な気持ちはなかったようで、強制力が働かなければ書く人になっていなかっただろう。これは、また逆に世には「書かざる潜在的文筆家」がたくさん存在するということを示している。
そしてまた、夫の泰淳の存在があったからこそ、日記は書かれる運命にあった。その証拠に泰淳が胃がん・肝臓がんのため64歳という若さで亡くなると、百合子さんは車を手放して運転するのをやめてしまう。それまで、富士への往復は頻繁をきわめていたが、運転は百合子さんである。泰淳は運転ができなかったし、するつもりもなかったようで、車内でひたすらビールを飲んでいるという様子が描かれている。
日記は、昭和39年(1964)7月に始まり、昭和51年(1976)9月に終わる。日記の最後の日付は、泰淳が病院で息を引き取る半月ほどまえである。
泰淳・百合子夫妻は東京では赤坂のマンション暮らしであるから、『富士日記』では、赤坂での生活の様子はほとんど山への出発時点や帰宅した直後のことしか出てこない。
この日記の魅力は、一言では表わせないが、人間に対する百合子さんの興味の持ち方が鮮やかに描き出されているのが第一に挙げられるだろう。山荘の隣人になった大岡昇平や中央公論社始め、各出版社の編集者という文壇内の人脈だけではなく、鳴沢村や富士吉田の地元の人たちとの言葉のやりとりが、ときには笑いを誘う。地元の職人や商店主など、彼らの人柄が自然に放出されて、目の前で話しているような臨場感を覚える。
地元の人たちの間で、百合子さんがとりわけ親近感を示すのは、石屋の外川さんとガソリンスタンドのおじさんに対してである。おばさんたちもしょっちゅう登場するが、地元のヘンテコな噂やエピソードを聞かせてくれるのはたいていおじさんたちで、百合子さんが耳を立てるように聞いてくれるためか、おじさんたちは一層話を面白くする。また、おじさんたちはオデンだのワカサギだの「食べろ、食べろ」と持たせようとする。百合子さんも、その都度、返礼の缶詰などを渡す。人付き合いが面倒な人には苦手な役割だが、生来人好きな百合子さんは、地元民との付き合いを楽しんでいるし、泰淳の作家仲間、出版社の編集者や新聞記者などともすぐに気脈を通じてしまう。何事も面倒くさがりと見える泰淳には、得難い伴侶だっただろう。
文学史では語られない交友・交流を知ることができるのが、この日記の魅力の一つと言っていい。たとえば、ウィキペディアで大岡昇平の項を調べると、大磯から成城に自宅を移したことは載っているが、富士の別荘については、記述されていない。私が持っている大岡のエッセイ集に「わが師わが友」という一章があるので、再読してみたが、武田泰淳については、晩年の交友のせいか触れられていない。だが、二人が同時に別荘滞在しているときには、毎日のようにお互いの家を行き来し、飲んだり食べたり、馬鹿話に興じたり、笑いこけたり、身体の不調を嘆きあったり。二人の作家は夜中に仕事をしているようだが、日記では毎日遊び暮らしているように見えるのは、妻は夫の仕事中は眠っているからだ。泰淳は気難しい人ではなく、温和な、争いを好まない性格のようで、付き合いの幅は大きくはなかったと想像できる。大岡は「喧嘩屋」の印象が強いが、無類の人好きであることが、百合子さんの日記から読み取れる。
13年の別荘暮らしの間に、何人もの「死」が語られる。私は自分が晩年の領域に入ったせいか、「死」について記述される個所がことのほか心に沁みる。
1965年、「桜島」の作家梅崎春生が亡くなる。50歳という若死にであった。武田夫妻ばかりでなく、娘の花さん(本名は花子)も梅崎には親しんでいたようで、三人の悲しみ方は尋常ではない。<主人も私も花子も、別々のところで泣く。主人は自分の部屋で。私は台所で。花子は庭で。>
梅崎とのこのような交流は文学史の表には決して浮かんでこない類のものだ。
愛犬ポコが亡くなるところも印象が深い。ほかの車に吠えて迷惑だというので、いつもトランクルームに籠ごと入れられて山に到着するのだが、籠の蓋が何かの衝撃で浮いて、首に伸し掛かり死んでしまうのである。涙が止まらない武田夫妻を慰めるのも、また大岡昇平だ。大岡は飼い犬の死をたくさん見てきたというので、その体験を話し、武田夫妻を元気づけようと心を砕いてくれる。「もういいだろう」と、大岡が帰ろうとすると、武田夫妻「まだまだ」。
ポコの飼い主は、娘の花だというので、まだ事情を知らない彼女に伝えなくてはならない。百合子は〈とうちゃん、言う?〉と頼むが泰淳は、〈俺は絶対いやだからな〉と仕事部屋に逃げていくのは、悪いけど笑える。善良な、いい夫婦だったのだ。
「死」についての記述のクライマックスは、最後に語られる泰淳の死である。亡くなった日そのものは、日記の最終記述日のまた半月後だが、『富士日記』は泰淳の死の直前で終わる。入院前、自宅で寝かされている泰淳は頭に変調をきたしているのか、缶ビールを飲む仕草を繰り返し、ビールを所望する。「かんビールをポンと……」。この場面は悲しい。
歳月というものを考える。百合子さんたちが、山荘で暮らしていた五十年前のあの日この日のことを。花さんのエッセイによると、百合子さんの死の何年もあとに別荘の建物は解体され、土地は更地になって、借地権も返上したとのことで、いまは「富士日記」の舞台は永遠に消えてしまったのである。
エッセイをここで終わりにするのは寂しいので、昭和42年(1967)8月20日の日記のところを最後に紹介する。
夜、百合子さんがひとりで運転して、山荘への暗い山道を走っていたとき。山ウサギが道の真ん中に躍り出てくる。クルマを避けて、沿道の草むらに飛び込んでくれればいいのに、ウサギはクルマの前を走り続ける。ときどき振り返って後ろを見る。百合子さんはスピードを落とし、ウサギが左側の草むらに逃げていくまで見送る。クルマを止め、草むらで息を殺しているウサギの気配を感じながら、百合子さんは涙を抑えながら〈長生きをおし〉と呟くのである。愛犬ポコが亡くなってから、ひと月くらいの時期だった。ウサギの健気さが百合子さんを感動させたのである。