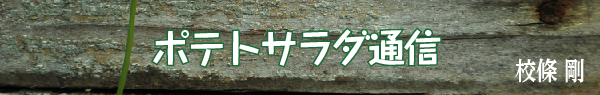ポテトサラダ通信 62
シベリウスを聴こう
校條剛
フィンランドを代表する作曲家シベリウス。この人の全交響曲集の四枚組のセットを持っています。
Amazonで廉価な輸入盤を購入しました。価格だけの理由ではなく、シベリウスを演奏させれば、随一という評判のフィンランド人、ベルグルンドの指揮だったからです。
私が持っているのは、イギリスのボーンマス・シンフォニー・オーケストラを指揮した録音です。録音時期は1970年代です。
ベルグルンドは、交響曲全7曲の録音を、このあと故郷のオーケストラ、ヘルシンキ・フィルとやり、最後にヨーロッパ室内管弦楽団(本拠ロンドン)と行なっています。
ベルグルンドに三つの録音があることは日本の愛好家にはあまり知られていないでしょう。というのも、クラシックのCDを推薦する書籍ではあとの二つの盤ばかりに話題が集中していて、ボーンマス盤には言及されていないからというのが原因と思われます。
ちなみにボーンマスは、イギリス南部の都市名で、リゾート地として有名だそうです。ロンドンからの直線距離は150キロ。そこに本拠を置いていたのですが、現在は近郊のプールをいう都市に移っているようです。地方オーケストラですが、シベリウスの作品の演奏を聴いて分かるのですが、かなり実力のあるオーケストラだったようです(現在の演奏は聴いたことがありません)。
さて、クラシックCDを選ぶときに指標とするべき書籍は意外と少なくて、そのほとんどがカラヤンという超人気スターの盤を推奨するか、反対にカラヤンを全否定して、地味な存在の指揮者を不自然に思えるほど持ち上げるかどちらかといっていいでしょう。
後者の代表例が文春新書の『クラシックCDの名盤』というシリーズです。「新版」とか「大作曲家篇」とか、このタイトルで都合三、四冊刊行されています。
このシリーズは三人の音楽家が担当しているのですが、一曲ずつ分担するのではなくて、三者が一つの作品について、推薦盤を述べる仕組みになっています。音楽の好みは確かに個々の聴き手によって違ってくるので、この方式はこれまでなかった新鮮な印象を与えます。
三人の音楽家とは評論界重鎮の宇野功芳、ベテラン音楽プロデューサー中野雄、合唱指揮者の福島章恭で、カラヤンを例に取ると、中野氏の他はカラヤン盤を推すことは滅多にありません。それでも、オペラに名盤の多いカラヤン盤を推さずには済まされない曲もありますので、まったく推薦しないというわけではありません。
私は中学のときから、クラシック音楽のファンですが、楽典のことはほとんど知らず、従って譜面を読むのも最低限の旋律だけでした。六五歳からサックスを習いだして、やっと拍子の強弱(四分の四拍子なら、「強・弱・強・弱」)を理解できたというほどの奥手だったのです。
そういう私が、クラシック曲のCDのあれこれを指して、この演奏がいいだとか、悪いだとか批評する能力があるとは思えないのですが、音楽というものは、聴き手が満足していればいいのであって、いくつかの同名曲のなかで、好きな演奏とそうでない演奏があるのは当然なのです。曲によっては、どの演奏もいい演奏だと思うことはありますし、反対にどれを聴いても昔耳にした感動が蘇らず不満足なことも。
私がここで述べるのは、素人ながら60年近くクラシックを聴いてきた人間の素直な感想だと思ってもらいたいのです。
私がべルグルンド/ボーンマス響のシベリウスを愛聴していることを述べました。この演奏について、さて、『クラシックCDの名盤』の著者たち三人はどのように評しているでしょうか。
宇野;全集のCDは迷うことなくベルグルンド/ヘルシンキ・フィルを選ぼう。
中野;バルビローリ/ハレ管他が古典的名盤。そしてベルグルンド/ヨーロッパ室内管が近年の秀作。
福島;基本的なライブラリーとして押さえておきたいのは、ベルグルンドのヘルシンキ・フィルとのEMI録音とヨーロッパ室内管とのワーナー盤である。
ほんのさわりだけの抜粋ですが、三者ともベルグルンドを強力に推していることがお分かりでしょう。しかし、ボーンマス響との演奏については、とうとう一度も触れることがないのは、このシリーズのたとえば「大作曲家篇」でも同じことです。
ボーンマス盤が他の二つに比べてそれほど程度の低い演奏なのでしょうか。
以下に紹介するのは、ネットで見つけた文章です。筆者名が記されていないので、固有名詞を示すことはできません。私が筆者名を省いてコピーしてしまったのかもしれませんが、読んでお分かりのようにこの世界にかなり通じた方の意見と思われます。
こうです――
〈クリストファー・パーカーとともにEMIのアナログ全盛期を支えた名エンジニア、スチュワート・エルザムによる名録音が2013年の最新リマスターで蘇った(クレジットには確かに2013年とあるが一体こんなに早いリリースが可能なのか疑問ではあるが…)。嬉しい事にリマスタリングも上々で、ヒスノイズは始終聴こえるし、楽音以外のノイズ成分もカットされていないことから、オリジナルマスターテープにほとんど手を加えず、フラットトランスファーしたものと思われる。 録音は72年から77年までの5年間に渡り、サウザンプトンのギルドホール、ロンドンのアビロードスタジオ、同じくロンドンのキングスウェイホールという3箇所でのセッションによるものだが、それぞれのホールが有する固有のアコースティックをエルザムは極めて正確にリスナーの前に届けてくれる。〉
と、かなり専門的な説明なので、後半の結論に飛ばしましょう。
〈ベルグルンドのシベリウス全集では80年代のヘルシンキフィルとのデジタル録音があまりに有名であり、ボーンマス響とのアナログ録音の影は薄いが、こちらの演奏の方がダイナミクスの幅は大きく、表情付けも濃厚なうえ、遅いテンポでシベリウス節をとことん歌いぬいている。さらにエルザムによるガッツのある豊饒な優秀録音がこれを大きく助長しており、ライブ的な臨場感やスリリング感においても本アルバムの方がはるかに上だ。 ヘルシンキとのデジタル録音も悪くはないが、演奏もやけにスッキリしているし、録音もどことなく綺麗に整った印象が強く、エルザム録音と比べてもDレンジは劣るし、ステージ奥のティンパニや金管群の重量感、解像度共に大きく水をあけられている。 これらの点から、ベルグルンドのシベリウス全集では、演奏上も、録音上も、それに価格の面からも、本アルバムをベストとしてチョイスするのになんの躊躇も感じないし、数あるシベリウス全集の中でもトップクラスの名アルバムとして広く聴かれるべきディスクである。〉
上記の太字部分は、私が加工したもので、この文章の筆者のものではないことを断わっておきます。
ここで私は大きな疑問符が胸のなかに灯るのを禁じ得ません。『クラシックCDの名盤』の筆者たち三人は、このボーンマス盤を聴いたことがあるのだろうか、と。
以前、新潮社からクラシック評論誌『グラモフォン』が刊行されていたことがありました。森重良太氏(音楽評論家としては富樫鉄火の名前を使っています)が誘致し編集長を務めていた雑誌です。この雑誌はイギリスの伝統あるクラシック音楽雑誌で、その翻訳版だったのですが、評論レヴェルの彼我の違いに驚いたものです。そもそも、一つの演奏を批評するのに聞いたこともない過去の演奏の例を持ち出して比較するとか、もちろんボーンマス響の演奏を批評した上記の文章のように録音したホールの特性まで言及していることもあったと思います。本場だから当然とも言えますが、日本の評論家はいささか情報が少なく視野が固まっていると思えてしまうのです。マイナーな音楽家を拾おうとしている姿勢は評価できるのですが、ボーンマス盤の存在さえも知らないのではないかと思えるような幅の狭さではとても私のような愛好家の好奇心は満足させられないのです。
ネットを検索すると巷の素人評論家の皆さんの奮闘振りが目立ちます。ボーンマス盤への低評価のものももちろんあります。「パワー不足、技術が劣る、ベルグルンドの若さゆえの未熟さが露呈している」というような評も実は沢山目にしました。
今回は他人様の引用ばかりで恐縮ですが、ネット検索で「なるほど!」と頷ける意見を拾えたので、以下に示しましょう。
〈最近はクラシック音楽業界も不況のために大家による再録音、再々録音などと言うことはすっかり影を潜めましたが、80年代ぐらいまではそういう企画がわんさかとありました。
レコ芸などではそういう録音がリリースされる度に天まで持ち上げる批評が紙面を飾っているので、まだ初だったユング君(注:このブログの作者)などはその言葉を信じてせっせとCDを買ったものでした。そして胸躍らせてCDプレーヤーにセットするのですが、そのほとんどは「上手い」事は認めるのですが、どれもこれも胸に迫ってくるもののない演奏が大部分でした。
手慣れた指揮と能力の高いオケによる演奏ですから瑕疵はほとんどありません。オケはそれなりによく鳴っていますし、アンサンブルも申し分はありません。楽曲の解釈も「楽譜に忠実」な隙のないものですからこれといって文句を付けたくなるようなところはありません。
でも、それらを総合して聞こえてくる音楽は「つまらない」のです。
ボーンマスのオケにとってシベリウスの交響曲を全曲録音するという営みは間違いなく「祝祭的出来事」であったはずです。
しかるに有名指揮者と有名オケによる録音は、決められたスケジュールのなかで次々とこなされていく「仕事」の一環でしかあり得ません。はたして、その録音のなかで、両者がともに持てる力を発揮してその限界ギリギリまでに自らを追い込んだのかといわれれば、答えは明らかにノーです。
音楽を演奏するという行為が「仕事」になったのでは、その営みがどれほど高いレベルでなされたとしても感動とは縁遠いものになるのではないでしょうか。少なくともボーンマスのオケからはそのようなルーティンワークの匂いはどこを探しても見つけだすことはできません。
オケの技術は上がる一方です。
でも、そんなに高い技術は音楽を演奏するために必ずしも必要ないのではないか?という思いが最近の私のなかで頭をもたげてきています。(by yung) 〉
(太字処理;校條)
ユング君に大賛成です!