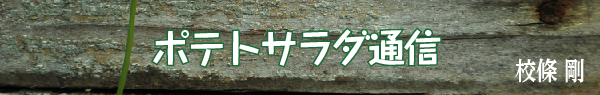ポテトサラダ通信 61
『われら闇より天を見る』の姉弟
校條剛
久々に素晴らしい本を読みました。クリス・ウィタカー『われら闇より天を見る』(鈴木恵訳)。海外ミステリー愛好者としては、一昨年読んだ『ザリガニの鳴くところ』以来の収穫でした。両作とも早川書房の単行本であるのは、最近のこの出版社の目利きの良さと、スタッフの充実、版権エージェントとの緊密な関係を想像させます。
この小説の最大の魅力は、海外文学作品の伝統的な特徴である「人間を描く」という基本をおろそかにしていないところでしょう。というよりも、謎とトリックの仕掛けよりも、個々の人物の陰影を探っていくことに重点があるようです。つまり、人物造形を優先しているのです。
以下の文章には「ネタバレ」に通じる要素が若干あるかもしれませんが、それでもこのあと、この小説を読もうという方々に迷惑を与えるような「バレ」方には配慮しているつもりです。
私が特に心を動かされたのは、ダッチェスという13歳の美少女と弟のロビン5歳(二人はそれぞれ、物語の後半では一歳年を重ねる)の姉弟関係でした。この姉弟の父親は、物語の最後まで不明であり、最初の時点では父親違いと皆が信じています。ダッチェスの認識も世間と同じなのですが、それだからといって、「あんたとは半分しか血がつながっていないんだからね」と嫌みを言うことはまったくありません。母親は破滅的な生活者で二人の世話が出来ないので、姉が母親代わりに朝起きるときから、夜寝付くまで幼い弟の面倒を見ています。ロビンの食事を作ったり、歯を磨いたり、着替えをさせるのもダッチェスの役目です。
ダッチェスはおよそ可愛げのない、暴力的な性向の女の子であり、よその子供にも周囲の大人にも簡単に牙を剥きます。ロビンがいじめっ子に痛めつけられたときには、相手を見つけ出して、倍返しの暴力などへっちゃらです。しかし、ロビンに対しては、聖母的な優しさで接し、ロビンが姉に対して怒って、頬を叩き、傷を付けたときにも、なんの文句も言わないのです。母にとっても、ダッチェスにとってもロビンは「王子様」なのです。
ダッチェスは、全面的に弟の庇護者であるので、食べものが一人分しかないときには、自分は我慢して、弟に食べさせます。あるとき、ホットドッグを一つだけ調達したときに、ケチャップだけが足りません。街の食堂で無料のケチャップの小袋をせしめるのですが、知り合いの子供に見られ、「何か買った人しか、貰えないんだぞ」と非難されるのです。そのあと、歩きながら「僕、ケチャップなくても美味しく食べられるよ」というロビンのセリフには泣けるものがあります。
幼いロビンはまだ世間知を持たず、常識というものに直面する年齢に達していません。本能と姉の指示するままに生活しています。一方、14歳のダッチェスはこの年齢でも世の中の辛酸を痛いほど味わっているので、すでに確固たる人生観、世界観が内部に作られているのです。しかし、だんだんとダッチャスとロビンの間には、小さな溝が表われてきます。
ロビンが一歳歳を重ねれば重ねるほど、その溝は徐々に生じてくるのです。母親が亡くなり、1,600キロも離れたモンタナ州(姉弟はカリフォルニアで生活していました)で、牧場を経営する祖父ハルの元に引き取られたときからその溝は顕在化していきます。
祖父に可愛がられ、ふんだんに愛情を注がれることに慣れていくロビンに比べて、ダッチェスは祖父が亡くなるまで、祖父が幼い姉弟に果たしてきた貢献には気がつかないのです。
ロビンが町の小学校で虐められ、ダッチェスはその犯人を叩きのめしたあと、「私がいいお家を探してあげるから。一緒に暮らせる場所を」と慰めるのに、対して「僕は爺ちゃんの家に帰りたいんだよ」と泣きながら言うのです。ここで、ダッチェスは気がついたはずです。
その後、いくつかの波乱があって、ロビンは養子として、子供のいない優しい夫婦に引き取られていて、その様子を密かにダッチェスは覗きにいきます。最初は声を掛けるつもりだったのでしょうが、ダッチェスはロビンがすっかり家庭に溶け込んでいるのを確かめて、黙って戻ります。実際は、姉の体温を求めて、泣きながら起きる朝もあったのでしょうが、ここではもうロビンの心細さは描かれません。時が経てば、最大の庇護者だった姉の存在も心のなかから消えていくのでしょう。ダッチェスはそれを分かっているようです。
私たちは幼い時期、小学校低学年くらいまでの出来事をほとんど覚えていません。小学校も三年生くらいになるとうっすらと蘇る光景もありますが、小学校入学以前の幼少期の記憶はほとんどなくなっていきます。
私にはいわゆる「腹違い」の姉がいます。私が幼いころには同居していましたが、私が小学校に入学するときには、もういなくなっていました。あとで聞いたところでは、名古屋の叔母のところで養子になるというので、引き取られていたのです。それから、何十年も会うことがなかったのですが、私の父親の死のあとからときどき会って、話をするようになりました。
私は兄と弟の三兄弟で育ちました。姉がいたころは兄だけでしたので、弟のことはほとんど知りません。私の兄は明朗で立ち回りが素早く、学校の勉強もよく出来る秀才でした。中学校のときには、生徒会長を務めるほどの社交性も持っていました。姿も痩せ型で背も高く、食べものの好き嫌いもありません。
一方の私はジメジメとして、はっきりしない性格で、教師に質問されても、ちゃんとした受け答えが出来ない鈍な子供でした。兄とはすべて対照的で、背は当時普通でしたが、太っていて「白豚」なんて呼ばれた時期もありました。食べるものも好き嫌いが多く、学業も低空飛行です。
しかし、姉が可愛がったのは、何かと鈍な私のほうです。姉は、生さぬ仲の私の母から愛情の薄さを感じ取っていて、心細い自分と一緒に手を結ぶべき相手が必要だったのでしょう。姉は眉目秀麗な兄が苦手だったのです。その分、余計に私を可愛がったわけです。
「天沼の平八郎叔父さんのところによく一緒に行ったこと覚えていない?」と姉は私に訊きます。私の手を引いて訪ねたのでしょうが、微少なカケラほどの記憶も残っていません。
兄と私が大通りを渡ったところにあった幼稚園に通っていたころ、帰りの時間になると姉が途中まで迎えにきてくれていたそうです。姉の姿が見えると、幼い私が嬉しそうに駆け寄ってきたのだと言います。「覚えていない?」と問われても、同様に記憶の保存はないのです。
記憶をすべて失った私の言葉に姉は悲しそうな表情を浮かべるので、私はいつも申し訳ない気持ちになります。
ダッチェスが見通しているように、ロビンはあまりに幼いので、ダッチェスがどれほどロビンを守ってきたのか、その過程をすべて忘れてしまうかもしれません。
しかし、ダッチェスとロビンには新しい姉弟関係が未来に開けています。この二人はフィクションのなかの姉弟なのに実在の姉弟であるかのように、私は声援を送ってしまうのです。この小説の偉大さがそのことで分かっていただけるのではないでしょうか。
*前回予告しました病院についてのブログは取りやめました。