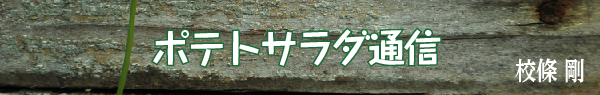ポテトサラダ通信 47
見たかもしれない空
校條 剛
エドガー・アラン・ポーの有名な詩「Annabel Lee」の原文は難しい言葉もなく、すらすらと読めるのですが、seraphという単語に関しては、意味が分からずに辞書を引きました。そのとき、突然、「セラフィック」という言葉が埃を被った記憶の山のなかから浮かび上がったのです。確か「熾天使的(してんしてき)」という形容詞だったので、セラフはおそらく熾天使だと想像し、辞書で確認するとその通りだったのです。
セラフィックという単語を知ったのは、はるか昔、高校三年生のときに読んだ加藤周一『羊の歌』(岩波新書)のなかでした。
『羊の歌』は、「わが回想」と副題が付された、加藤周一の自伝的なエッセイで、奥付を見ると、1968年8月に、さらに続編の『続羊の歌』(同)が、ひと月あとの9月に出ています。
それぞれ、私は初刷で買っています。『続羊の歌』には、新潮文庫のカバーが掛けられていて、裏に「川南書店」という印刷文字が記されています。東京都杉並区荻窪一丁目にあった小さな書店で購入したことが分かりました。
ついでながら、この書店は私の卒業した桃井第二小学校に近く、中学一年のときには角川文庫・上中下三巻のスタインベック『怒りの葡萄』も買いました。
残念ながら、川南書店が消滅してから、かなりの年月が流れています。荻窪では北口の公正堂(文字?)が当時、大きな老舗書店でしたが、川南書店のような小さな書店でも文庫や新書が並べられていたということなのです。
今回、このエッセイを書くに当たって、『羊の歌』二冊のなかで記憶に鮮明な部分を読み直してみました。余程心の深い部分に触れていたのでしょうか、「ああ、ここだ、ここだ」と鮮明に「あの時のあの時間」が蘇ります。文章の一々に思い出が宿っているのは、何度かこの本を読み直した証なのでしょう。
現在の「私という人間」の何分の一かは、正続の『羊の歌』に負っていることが、人生の晩年に入った今、やっと認識できました。二十歳直前の人間の将来に大いなる指針を与えてくれた「事件」だったことが、はっきりと分かったのです。
加藤周一という作者は、一部の知識人の間では著名でも、高校を卒業したばかりの、たいして読書家でもない若者には、決してビッグネームではなかったと思います。その人の本をどうして読む気になったのかは、さすがに記憶は戻りません。
冒頭に述べた「セラフィック」という言葉は、『羊の歌』の終わりに近いページにでてきます。太平洋戦争の敗色が濃く表われ始めた時期の東京本郷、東大病院。灯火管制のための幕を窓に下ろした一つの病室においてです。加藤周一はそもそも東大の医学部の学業を終えて、そのときは東大病院の医局員でした。訪ねてきたフランス文学者の森有正と一緒に蓄音機でセザール・フランクの「交響変奏曲」を聴くのです。
<「これはほとんどアンジェリック(天使的)ですね」と私は言った。「その通り」と森さんはいった。「ほとんどセラフィック(熾天使的)です」。>
ベートーヴェンやバッハではなく、フランス近代の作曲家フランクであるということが、この二人の教養の高さを示しています。実は、私はこの箇所を再読するまで、フランクの当該曲は「交響曲ニ短調」とばかり思い込んでいました。『羊の歌』を読んでから、数年後、交響曲ニ短調を聴きながら「これが、セラフィックなのかな」と首を傾げたことを思い出します。交響的変奏曲を聴いたのは、なんと加藤さんたちが聴いてから、八十年近くあとということになるでしょうか。
『羊の歌』『続羊の歌』のどの部分が、私の精神に多大な影響を与えたかということでは、いちいち上げていけば切りがないほど、その全体が私の血肉となっています。
何カ所も言及したいところが目に付くのですが、いちいち挙げていくとキリがありません。
そのなかで、一つ、亡き佐木隆三さんとの思い出に結びついているエピソードを話しましょう。
私が文芸編集者として、まだ駆け出しのころに担当して、何度も仕事をご一緒した佐木隆三さん。労働者文学からキャリアを始めて、中年になってから『復讐するは我にあり』を発表、この小説が直木賞を受賞すると同時に、一躍流行作家となり、無数の犯罪ドキュメント小説を著わし、犯罪・裁判・事件の専門家として世間から認知されることになります。
佐木さんとは、何度も犯罪の現場に同行し、裁判を傍聴して、事前取材をサポートしました。午前四時に起き出して執筆を始める佐木さんは、お会いする昼間には執筆は終わっており、まずはビールということは当たり前のことでした。そうした折りに、犯罪者に対する、特に殺人犯に対する処罰に論が及ぶこともありました。
私は原則、死刑賛成論者ですが(加藤周一さんは恐らく反対論の方だったでしょう)、佐木さんは、「この男は死刑にするべきだ」と言い切ることは一切ありませんでした。刑罰を言い渡すのは、裁判官の役目というのが、佐木さんの考えだったのです。
感情を排して事件の詳細を事実をもとに描くことが自分の仕事なのだという信念を持っていました。
私には、そういう処罰感情の薄弱さに不満を感じることがなかったとは言えません。加害者の人権ばかりが保護され、被害者はもう死んでいるから人権は消滅している、そのため保護する必要がないと言わんばかりの司法のあり方に憤激といっていいほどの怒りを日頃から抱いていたからです。
佐木さんは、「殺された人」の無念さを述べる私の考えの基盤を知りたがりました。しかし、論理的に死刑の正当性を述べることは難しいことです。何かに譬えて表現する、つまり比喩として述べると、人の考えは伝わりやすくなるものです。その流れで、私の口から出てきたのは「見たかもしれない空」という言葉でした。つまり、殺された人が生きていさえすれば、青い空を見たかもしれないし、その抜けるような青い色に人生の喜びを感じたかもしれないという意味の言葉です。
佐木さんは、この言葉が余程印象に残ったものか、その後、何かと「見たかもしれない空ですね」と呟くことがありました。
『羊の歌』との関連を述べなくてはなりません。再読してその部分を見つけました。この一節が、どれほど私の骨身に染みていたのか、稲光のように一瞬で理解できました。それなのに、今日まで、まったく気がついていなかったのです。少し長いですが、その数行を引用しましょう。
<しかし中西は死んでしまった。太平洋戦争のいくさ全体のなかで、私にどうしても承認できないことは、あれほど生きることを願っていた男が殺されたということである。生きることを願っていたのは、むろん中西だけではなかった。しかし中西は私の友人であった。一人の友人の生命にくらべれば、太平洋の島の全部に何の価値があるだろうか。私は油の浮いた南の海を見た。彼の目が最後に見たでもあろう青い空と太陽を想像した。(中略)愛したかもしれない女、やりとげたかもしれない仕事、読んだかもしれない詩句、聞いたかもしれない音楽……彼はまだ生き始めたばかりで、もっと生きようと願っていたのだ。(中略)太平洋戦争のすべてを許しても、中西の死を私が許すことはないだろうと思う。>
「見たかもしれない空」の「出典」について、佐木さんと話しがしたいと痛切に感じます。しかし、数年前、佐木さんは空の上の人になってしまい、あの目を細めた笑い顔と甲高い声を思い出すばかりなのです。