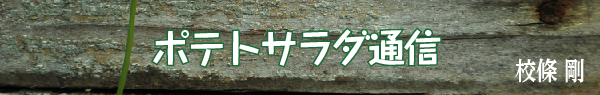ポテトサラダ通信 31
不倫は文学だ
校條 剛
有名人の不倫は、テレビや週刊誌の恰好のネタになる。現時点では、渡辺謙の娘・杏の夫である東出昌大と唐田えりかの不倫騒動がなかなか止みそうもない。テレビや週刊誌の記者達の多くも不倫経験ありと想像するのだが、他人の不倫には不寛容な態度をとり、興味が満たされるまでほじくり回し、まるで犯罪者のように晒し者にする。当該のタレントを使ってテレビコマーシャルを打っている企業も、スキャンダルの渦中にいる彼らをコマーシャルに登場させることを避けたがる。今回の東出さんももちろん、コマーシャル業界から追放されそうである。
不倫してもいいじゃないかとは言わないが、不倫と名付けられるかもしれない男女関係に追い込まれる(あるいは、好きで入り込む)経験は社会人なら大方の人にはあるのではないか。え、ない? それは失礼しました。
私が心配するのは、こうした不倫叩きを幼いころから目撃してきた若い人たちが、「不倫は絶対悪」と思い込んでしまうことだ。我々(団塊世代くらいを想定)の時代には、もちろん不倫という言葉はあった。だが、テレビのニュースショウでここまで大々的に不倫叩きをする光景はなかったように思う。
そもそも、私が少年時代から読んできた小説や観ていた映画には当たり前のように不倫関係にある男女の恋愛が描かれていた。アメリカの映像作品は、そもそも清教徒の国だけあって、子どもと大人が一緒に観られるように作られているが、ヨーロッパ、ことにフランス文学・映画では不倫という言葉などこの世に存在しないかのようにごく普通の男女関係として描かれていた。フランスは、アメリカと違って、子どもと大人の線引きが厳格な大人の社会であるからこそである。
文学において、不倫は当たり前というより、むしろなくてはならない重要なファクターだと思う。
京都の私立芸大で教えていたときに,私がショックを感じたのは、学生の大半が「不倫は悪」と問答無用で信じていることだった。
私が所属していたのは、「文芸表現学科」といい、一般の大学では「文学部」に当たる学科だったのだが、文学部と違うのは、まず語学をやらないこと、研究よりも創作に重点を置くことであった。大半の学生は、小説を書きたくて入ってくるが、純文学やミステリー志向は少なく、大部分はファンタジー派であった。
小説は、ひたすら書いていれば上達するものではない。「読み、かつ書く」という両輪が回ってこそ作品はよくなる。その目的に添って、古今の名作・傑作を読み、感想を述べ、意見を闘わせるという「百讀」という二コマ続きの授業が設けられていた。名前の通り、この授業が始まった当初は、百冊の純文学を読むという決まりだったのだが、読めないまま単位を落とす学生が続出したので、大幅に冊数を減らしたという経緯がある。
私は、後期にこの講座を担当して、純文学だけではなく、エンタメも課題リストに入れたのである。
何回目かに、アントン・チェーホフの短篇「子犬を連れた奥さん」を一年生に読ませた。この小説の舞台は、黒海に面した避寒地のヤルタ。裕福な人種が倦怠感に溢れた時間を持て余して、カフェや海遊びで日々を過ごしている。銀行員のグーロフは家族を連れず、ひとりでここに来ていた。そして、海岸沿いのレストランで白い子犬を連れた婦人を見初めるのである。いつも寂しげな彼女をモノにしようと企み、見事目的を達する。
彼は軽い遊び心で、婦人に近づくが、だんだんと彼女の汚れのなさに打たれ、自分でも思いがけず深入りしていく。別れの日はたちまちやってきて、婦人と子犬は去っていく。もう一生会うことがない二人のはずだった――。
18世紀のヨーロッパでは、フランス、イタリア、ロシアなどは、堅固な貴族社会が形成されていて財産を相続すると、一生どころか永遠にお金は困らない生活が出来た。それで、夫も妻も自分自身の財産を持っていることが多かったのだ。妻は、経済的に夫への従属関係がなかったので、形としては夫婦でも、それぞれ独立した存在だったわけである。
裕福で文化的な教養の豊かな婦人達が友人知人達に交際の場所を提供し、芸術家や政治家や外交官、あるいは他国から流れてきた論客などを招いて、彼らの機知を闘わせる「サロン文化」はこうして生まれた。スタンダールはイタリアのサロンの常連客で、サロンを主催する婦人たちに言い寄るのを常としていた。『アンリ・ブリュラール伝』というスタンダール自身の自伝には、これまで彼が愛人として交際してきた十人以上の女性の頭文字を地面に書き付けるシーンが描かれている。その十人はほとんどか、すべてがいわゆる人妻である。
――人妻ゆえにわれ恋めやも
なんて歌が万葉集にもあるそうじゃないですか。日本にだって、古代より人妻に言い寄る文化があったのである。
さて、チェーホフに戻る。「子犬を連れた奥さん」のテーマは、肉体関係を超えた本当の愛ということになるか。そう言ってしまうと通俗そのものだから、寂しさに耐えている男女の出会いと希望とでも言おうか。それは帝政ロシア末期の時代がまとった退屈と怠惰と停滞の毎日を生き生きとした人生に切り替えてくれる重要なファクターであるはずだった。お互い伴侶のある男女ではあるが、愛し合うべき相手と結ばれないことの悲劇を、私は学生時代に深く心に刻んだのであった。
「百讀」の授業で驚いたのは、このテキストを読んだ学生諸君が、極めて無感動に「これ、不倫の小説ですよね」とそれだけで切り捨てようとしたことだ。愛ゆえに結婚相手を決めたわけではない二人が、やっと本来一緒にいるべき相方と巡り遭った、そのことに若い私はどんなに二人を励まそうともがき、時代と制度とお金に縛られている彼らの未来が明るいものになってほしいと願ったことだろう。
今の学生達のほとんどが、この小説から感動をひとカケラも受けることもなく、「どうして不倫の小説なんか読ませるのか」という迷惑顔だったのである。
現代においても、他大学の文学部の学生、とくにロシア文学を専攻するような学生はまた違う感想をもち、ひょっとすると私と同じ感動を持つこともあるだろう。
私の大学の学生達は文化的なシャワーをどのように浴びてきたのか。おそらく、外国文学に親しんだのは『ハリー・ポッター』シリーズなどの魔法ものくらい。昔の文学青年が親しんだ世界文学全集などはお呼びではない。あとは、国籍不明のアニメとゲーム、コミック。国籍不明というのは、「ワンピース」なんぞを思い浮かべていただければいい。文学というよりもコンテンツと呼ぶのが相応しい文化シャワーを浴びてきた人たちだ。
アニメにもゲームにも、「不倫」は登場しない。これらのコンテンツは基本的に「類型」的「社会常識」的な考えを基盤として作られているので、類型の「愛」はあっても、複雑で背徳的な「不倫」が登場することはない。アニメとゲームは、その意味で健全過ぎるほど健全な精神から出来上がっている。ただし、ゲームの基本は相手を倒すこと。リアルの世界に置き換えると、実際に相手を殺すことになる。つまり、ゲームとは健全な精神を保ちながら、相手方の人間を平然と殺していく反人間的システムなのである、と断定してしまおう。
こういうシステムのなかに小さいころから取り込まれてきた若者は、不倫はしないが、実社会で簡単に人を殺す人間なることも可能である。思い当たる事件がありませんか?
話が大きくなりそうなので、また小さくフォーカスしよう。アニメやゲーム、コミックという類型世界で育った人間は、不倫というものはやってはいけない「悪」だと考えていて、小説の世界においてでも、それを拒絶してしまうのだ。
それでいいのか? 名だたる世界文学は不倫のオンパレードだ。『赤と黒』『ボバリー夫人』『アンナ・カレーニナ』『三人姉妹』などなど。日本の小説では大岡昇平の『武蔵夫人』がすぐに思い浮かぶ(大岡はスタンダリアン)。
『源氏物語』はどうするのか? これこそ、日本国が誇る究極の不倫小説。まあ、学生達が読む心配がないからいいってことかな。