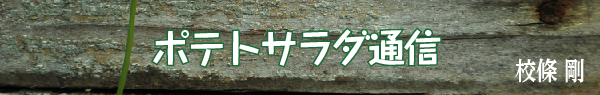ポテトサラダ通信 15
三浦圭一さんのこと
校條 剛
三浦圭一さんのことを書こうと思う。
三浦さんは、2006年から私が出向していたPという電子コンテンツ制作・配信の会社で同僚だった人で、今年、10月20日にガンで亡くなった。まだ62歳だった。
三浦さんを初めて知ったのは、私が新潮社からそのPという会社に出向したときである。私はミリオンセラーの『国家の品格』を作って、社員表彰などを受けた直後だった。出向のことを著者の藤原正彦さんに報告したら、「なんで、功労者を出向させるのですか」と不思議がられたが、ほかの部署に移りたいと社長に頼んだのは実は私自身であった。その折の詳しい経緯はここでは述べないことにする。
Pで過ごした4年間は意外にも私に望外の休息を与えてくれた。休息でもあり、また新しい領域を経験するというご利益もおまけに付いた。Pはソニーが中心となり、講談社、新潮社という二つの出版社と、大日本印刷、凸版印刷という大手印刷会社の都合五社で実質的な運営をしている組織だった。出版社側の権利制限がきつく、ソニーが企てた電子書籍のプラットフォーム作りは、時期尚早であることがすでに見えた時期に我々は赴任してきた。日本に電子書籍を定着させるための必要な条件が整っていなかったわけだが、あれから十年経った現2016年段階でも、さほど事情は変わっていないように思える。悪条件のなかで、なんとか沈みゆく会社を長持ちさせられないかと苦闘したのが三浦さんの人生最後の十年だったと言えようか。
元ソニーマガジンズの専務だった三浦さんがどうして、その地位まで上り詰めた会社を辞めざるを得なかったのかは、いちいち聞かないようにしたが、要するにソニーマガジンズの業績がひどく悪くて、その責任をとったのだと思う。
私は新潮社からの出向者で、三浦さんは講談社から雇用されるという立場だった。私は与えられた役割を無難にこなしながらも、それまでのように会社の仕事を最優先することはなく、自身で本を書くこと、大学やカルチャーセンターで教えることに重点を置いていた。Pでは三浦さんと違って、気楽な立場の「お客さん」だった。
三浦さんはそもそもCBSソニーに入社したのが社会人としての出発だった。私よりも四つ歳下だが、私のころと就職の状況はそんなに変わっていなかっただろう(オイルショックというのが、その四年の真ん中に入ってはいるが)。
というのも、私も新潮社を受けるまえに、CBSソニーを受けて、いとも簡単に落とされていたからだ。私はディレクター志望だったが、譜面を読めず、楽器もできないと堂々と話したところ、面接官の面差しが険しくなり、一瞬にして落とされてしまった。ま、当たり前だろうが、当時、音楽好きの(クラシックでもロックでも)学生には、CBSソニーは憧れの会社だった。受験者の数も相当なものだっただろう。だから、最初の面接は流れ作業のようにとんとんと進んだ印象があった。この難関の会社に受かった三浦さんはそもそも音楽の素養があったようだ。慶應では、ずっと音楽のサークルに属していたのだと思う。そのサークルでか、CBSソニーに入ってからかはわからないが、いまや大物歌手の仲間入りをしている某女性歌手と同棲なんぞもしていたというのも、彼の優しい穏やかな人柄を考えると納得がいく。
三浦さんと私は、実は生い立ちに共通点があった。彼のそもそもの出自は長野県の佐久で、檀家総代であるほどの有力者の家柄だったから、父上が晩年に新築してすぐに亡くなってしまったという実家も継いでいたが、本人は神戸で少年期を過ごしている。神戸高校卒業と聞いたが、小学校が私も在籍した、六甲山の麓にある高羽小学校だった。私は、二年生の後半から四年生までの二年半くらいそこにいたので、四つ下の三浦さんは、私が四年生を終えて、名古屋に引っ越した春に入学した計算になるのだ。
時期は重なっていないが、小学校の近くに住んでいたことは間違いがないから、小学校の近辺ですれ違っていたとしても不思議はない。人は未来など見通すことはできないのだが、振り返ってみると、本当に不思議な人生の交差というものはあるものだとつくづく思う。
そういう共通点もあり、また穏やかな笑みを絶やさない温厚な三浦さんは私のような矯激な性格の持ち主とはいいコンビになった。
会社の人数は立ち上げ当時の半分以下に減っていた。社員、契約社員合わせて15人ほどだったろうか。その半分はソニ―からの出向者とソニー側の契約社員である。
三浦さんは、元ソニーの人間とはいえ、私と同じような業務に従事していたので、自然私と行動パターンが一緒になる。だいたい、12時から13時くらいの間に、「ランチに行きましょう」ということで、二人ぶらぶらと飯田橋のビルを出て、近辺の和食、イタリアン、中華、フレンチ、韓国料理、うどん屋と日替わりで新しい店を開拓する。気に入った店にはたびたび訪れる。食事のあとは、また必ずチェーンのカフェに入るのだが、三浦さんは結構なヘビースモーカーだったので、外苑東通りに面した「カフェ・ド・クリエ」などでは必ず喫煙テリトリーを選んだ。喫煙に関しては私が常に譲歩していたのである。
三浦さんの、私が知る限り唯一の「悪徳」はこの喫煙という習慣だった。酒はほとんど飲まないというか飲めない体質だったので、勢い煙草のほうに比重がかかる。人間、仕事をしている限り、ストレスから免れることはない。酒を飲むか煙草を吸うかしないで、人はどうやって日々過ごしていけるだろうか。
もしも三浦さんが喫煙の習慣を持っていなかったら、もっと長生きしていたかもしれないが、「もしも」は所詮、もしも、である。ガンになるのも寿命のうちと考えるほかないだろう。
Pからソニー勢が引き上げて、会社を縮小することになり、九段下のうんと小さなオフィスを探してきたのは私である。そこにまた二年ほどいて、私は新潮社の定年と同時にPを去った。
Pの社長は新潮社のOBで私より数年先輩の営業出身者に替わっていたが、この人物が口だけ達者で実務ができない人間だったので、経営の責任が三浦さんにのしかかってきた。私も辞めてしまったあと、三浦さんは無能な社長と働き者だが追及の厳しい女性陣の間にはさまって一人、運営、営業、コンテンツ開発、システム維持などの諸業務に邁進しなければならなかった。
三浦さんの未亡人と電話で話したときに、三浦さんが自宅では一切会社の仕事の話をしていないことを知った。私など自宅で愚痴や悪口ばかり述べ立てて女房を閉口させていたのとはエライ違いである。
2016年ももう最後の月に入った時点で、このエッセイを書いているのだが、今年の初め、2月の中旬に暫くぶりで三浦さんに会った。抗がん剤治療が一段落して、Pを買収した新興企業のオフィスでまだ少しむくみが残っているが、まぎれもなく三浦さんその人の顔に正対したのである。
そのあと、オフィス裏の四谷三丁目・荒木町の迷路に分け入り、狭い階段を登った二階の店でランチを一緒にとった。平日は二人でランチに出かけ、長いときには二時間も会社に戻って来なかったというくらい共通の時間を過ごしていた頃から5年以上も月日が経っていた。
三浦さんがその当時を思い出しながら笑う。「メンジョウさんは、バイキングとなると目の色が変わったもんなー」と。そうそう、と私も笑わざるをえない。バイキングが売り物の店がオフィスの近所に二軒ほどあったのだ。あの日々が戻ってきたようで、この上なく幸せなひと時だった。こうした気持ちは家族には絶対に分からない。結局、これが二人の最後のランチになってしまった。
私が10月に出した絵葉書は、なぜか藤田嗣治の自画像の絵葉書だったが、そこに「また一緒にランチしましょう」と書いた。亡くなる前日だかに、病院のベッドでその葉書を読んでくれたようである。
また、どこかで会えれば一緒にランチしたいなと本気で思っている。