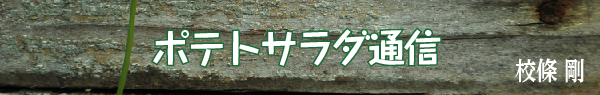ポテトサラダ通信 55
李御寧(イ・オリョン)先生のこと
校條 剛
堤伸輔氏が、主要キャスターとして出演している日曜日のテレビ番組を見ていて、嬉しく思いました。堤氏は出版社・新潮社社員時代の後輩なのです。いま彼はフリーになって、国際ジャーナリストという肩書のようです。
堤氏からの連想で思い出したのは、韓国の学者で一時は政治家でもあった李御寧(イ・オリョン)先生のことです。李先生の消息を聞かないまま、何年も経っていて、しかも日本における先生の代理人だった三木敦雄さんはかなり前に亡くなられていますから、そもそも情報源がありませんでした。
夜、眠れないままスマホをいじっていたとき、李先生の名前を入れて、検索をしてみました。すると、予感通りというか、先生も亡くなられていたのです。ただ、驚いたのは、その日が今年の2月で、しかも26日、私の誕生日の翌日だったことです。享年88。誕生日の日には、私は京都のホテルで講演をし、その翌日は暢気に京都太秦の町を歩いていたはずです。新聞を読んでいなかったために、訃報を今日まで聞かなかったということになります。
私が三十年に垂んとする文芸編集から、教養新書の編集に転身しようとしていたときに、この分野に詳しい堤氏に相談を持ち掛けました。親切にも、いくつか示してくれた名前のなかで、興味を抱いたのが李先生だったのです。
『縮み志向の日本人』(学生社刊)という著作でベストセラーになった学者だということも初めて知りました。どの分野で働いていても、世間の話題に敏感で、広い世界を見渡している人はいるものです。私もそのうちの一人と自負していましたが、この話題になった文化論を知らなかったのですから、やはり井の中の蛙だったのでしょう。
さっそく、代理人の三木さんと会い、李先生の意向を聞いていただくことにしました。すぐに、返事があり、いま書きたい題材があるとのこと。久しぶりの日本論壇登場なので、ひょっとすると『縮み…』以来のヒットを飛ばすことができるかもと、ひそかに期する気持ちが膨らみました。
李先生とは都合四回ほどお会いしたのではないでしょうか。最初は、神戸のポートアイランドに立つホテルだったと記憶します。三木さんは、常に一緒で、単独で先生と会ったことはありませんが、全幅の信頼が置かれている三木さんが同席していることで、心強い思いでした。
三木さんは、学生社に在籍中、李先生の知遇を得たとのことで、当時はすでに独立して、ミキ国際情報センターという会社を経営していました。
李先生の説明では、今度の本は「ジャンケン」についての論考になるといいます。ジャンケンは、グー、チョキ、パーの三つを同時に出すと、誰も勝ち手がいないと。しかし、考えようによっては、全員が勝者である。全員がウィン、ウィン、ウィンなのだと。グー、チョキ、パーを中国、韓国、日本の三者に当てはめて、三国の関係は全員がウィン、ウィンの関係になるのが望ましいというのが、今度の本のテーマなのだと先生は、早口で説明します。ジャンケンに例えた東アジア文明論ということになるようでした。
ジャンケンについては、先生が何年か前に、京都の日文研で客員として呼ばれていたときに、オーストリアの学者セップ・リンハルトが同じ客員として近くにいたことがアイディアの誕生に寄与したようでした。リンハルトさんは、日本文化研究家で日本滞在中の研究で『拳の文化史』を著わし、ジャンケンの歴史に詳しかったのです。
リンハルトさんの研究におんぶするのかなと最初、私は危ぶんだのですが、『拳の文化史』を読むに及んで、その心配はないことを確認しました。
執筆に二年ほどかかったでしょうか、原稿が出来上がったというので、HISのツァーで、三木さんと私は、ソウルの先生の元へと向かいました。
名家の生まれである先生の家は高台にあり(お金持ちはどの国でも高台に家があります)、奥さんも大学の先生でもあるという学者一家ですから、自宅のほかにもう一軒仕事場を持っていました。
仕事場のほうに移るまえに、先生が不思議な部品をパソコンから抜いているのを目にしました。パソコンは自宅に置いておいて、その小さなスティック状のデバイスを手にしていたのです。あとから知ったのは、それがUSBメモリーだったのですが、パソコンで仕事をしていた私の編集部でも使用している人間はまだいなかったのです。韓国はデジタル先進国ですが、すでにこの時点で抜かれていたのです。
それはともかく、メモリーを立ち上げて、その画面を見せながら、先生曰く、「原稿は550枚ほどになった」と(一枚は400字です)。それを聞いて、私はびっくり仰天です。新潮新書の規定の枚数は180枚だったからです。多くても200枚を上限とするというのが、創刊時からの厳しい掟ですし、そのことは口がすっぱくなるほどお伝えしていたからです。
もう一度、枚数制限のことをお話しして、350枚は削っていただかないといけない旨申し上げました。すると、先生は激昂して、「それは、もう私の作品じゃない!」と。もうこの仕事から降りると言われます。
三木さんも必死に宥めに入りますが、先生の怒りは収まりません。ちょうどお昼の時間だったのか、韓国風中華の豪華なお皿が届いていたのですが、食欲は吹き飛んでいて、三人ともちょっと口をつけるだけでした。
先生の怒りが収まらないままに、夕方またお邪魔して、先生行きつけの焼肉料理屋に向かうことになりました。
恐る恐る高台のちょうど真下に位置する高級な焼肉店に入り、先生の到着を待っていますと、にこやかな笑みを浮かべて先生が部屋に入ってきました。ホテルから、三木さんが電話をして、一応の解決へと向かうように塩梅してくれたのではと推測しました。それほど、先生と三木さんの信頼感は強かったのです。
長めではありましたが、なんとか新潮新書の規範内の枚数で収まった原稿の疑問箇所解決のときには、三木さんに新潮社に来ていただき、会議室の電話からソウルの李先生に確認作業をしました。終わったのは、もう夜の一時頃だったのではないでしょうか。
千葉県四街道市に住んでいた三木さんには、会社のタクシー券でお帰りいただきました。タクシー券がふんだんに使える良き時代でした。
そのような思い出のある李御寧先生の新潮新書『ジャンケン文明論』は、なぜか書評でも注目されず、売れ行きも芳しくないまま消えてしまいました。
このエッセイをお読みになって、ご興味をお持ちになられた方は、ぜひネットの古本書店でお買い求めください。
李御寧先生と三木敦雄さんのご冥福を心よりお祈りしたいと思います。