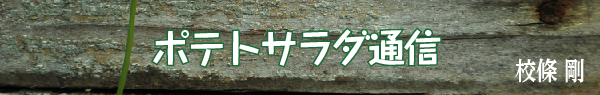ポテトサラダ通信 11
中一弥さんのお盆
校條 剛
もうそんなに歳をとったのかなあ、とため息が出る。今年は特に親しい方々の訃報の多い年でした。
春に船戸与一氏、夏に木田安彦氏と阿川弘之氏、10月の終わりから立て続けに佐木隆三氏、中一弥氏、そして止めに宇江佐真理さん。高槻市に長いこと暮らしていた私の伯父(母親の兄)が100歳を迎え、内閣総理大臣からお祝いの銀杯が届けられて間もなく4月に亡くなったことも夏になってやっと知らされました。皆さん、私よりも年上といいたいところですが、宇江佐さんは私と同じ学年、いわば同級生でした。
私ももう人生の黄昏に差し掛かっていることは事実なのでしょうね。ですが、私よりも二つ先輩のヒラリー・クリントンさんが、次の大統領になるかもしれないという状況はたいへん喜ばしいです。アメリカ民主党の支持者でもヒラリーのファンでもありませんが、私よりも年上の女性が世界で最も激職とされる大統領になるかもしれないのです。亡くなった方々を偲びつつも、ヒラリーのように前だけ向いて生きていけたら素晴らしいなんて、殊勝な文句を思い浮かべているこのごろですが、今回は亡き人のお一人、40年以上のお付き合いになる挿絵画家の中一弥氏の想い出を述べたいと思います。
私が新潮社に入って、すぐに配属されたのは月刊小説誌の「小説新潮」。1973年4月のことです。中さんは、当時、池波正太郎の「剣客商売」シリーズの挿絵を毎月描いていました。対抗誌の「オール讀物」では「鬼平犯科帳」の挿絵も中さん。この二つのシリーズほど頻度は多くなかったと記憶しますが、「小説現代」では「仕掛人 藤枝梅安」のシリーズもやはり中さん。池波正太郎の人気シリーズは一手に中さんが引き受けていたんです。
中さんの家は荻窪の川南という、以前に私が通っていた中学校の通学路途中にありましたので、私にはいわゆる土地勘があったのです。入社のときには、私の家は荻窪の線路を挟んで北側に移動していましたので、中さんの家は反対側になっていましたが、出勤前に絵を貰いに行くのに、私は適役でした。
もちろん、入社したてで、まだ担当作家なるものは数えるほどしか持っておりません。池波さんのような大物には、ベテランの編集者がついていて、私は挿絵取りだけのお使いさんです。
中さんの家は奥行きが深い面白い間取りでしたが、玄関の入り口は狭く地味で、挿絵の大家が住んでいるところとはとても見えませんでした。
表札には本名の「中福寿」とあり、私はこちらのほうがペンネームみたいだななんて思っていました。後に作家になった三男の逢坂剛(本名・中浩正)さんが、私が通い始めた時期にもその家から博報堂に通っていたと知って、大いに驚いたものでした。
中さんのお宅に伺うと、まずたいてい絵が完成していることはありませんでした。しばらく完成を待つことになります。いつも必ず、クリープ入りのインスタントコーヒーが供されました。応接間と台所(?)の仕切りとして掛けられていた玉すだれの形状もありありと思い出します。そのころは、随分と若くて背が高い奥さんだなと思っていた感じのいい女性が出してくれたのです。だんだんと分かってきたのは、三男を産んでから奥さんを亡くされた中さんは、暫くして家事の手伝いのために遠縁の女性、上田さん(確かこのお名前です)を呼び寄せたのだということでした。
私が新潮社に入ったのは、1973年ですから、現時点からすると42年前ということになります。中さんは先日104歳という超高齢で亡くなられたわけですから、1973年には62歳だったことになります。そのころは、会社員の定年が60歳ですから、勤め人だと会社を定年になっているとか、嘱託で勤務を続けているかという年齢です。現在の私の年齢よりは若いですが、まあ、似たり寄ったりです。私を中さんに置き換えてみると、私はさらに今から40年先まで働けるということになります。40年ですよ、40年。生まれたばかりの子供が40歳になると、もう中年と呼ばれますよね。それだけ、長い年月、普通なら定年後を迎えた人が絵を描き続けたのです。
引っ越し魔だったという中さんはそれから数年して、今度は練馬区氷川台の少年鑑別所の近くに引っ越しをしました。その家では、ふすまの表面に大きな江戸切絵図を貼り付けてありました(糊を使ったのではなく、鋲ででも留めていたのでしょう)。氷川台は当時作家の綱淵謙錠さんがいましたし、後に田中小実昌さんも移ってきたのですが、どこにあの土地の魅力があったのでしょう。そうそう、綱淵さんの原稿をしょっちゅうコピーしているうちに、文房具店の女性店主と親しくなったこともありました。彼女は、「小説新潮」の愛読者になってくれて、ときどき「読者の声」欄に投稿してくれました。短歌の結社に所属していて、歌集をいただいたこともあります。癌で亡くなられたあとに、店を継いだ息子さんから、遺稿歌集を贈られたときの寂しさを思い出します。
もううろ覚えなのですが、私が「小説新潮」の編集長だったころに、中さんと逢坂さんの二人を下町に誘い出して、グラビアページを作ったことが確かあったと思います。ワンボックスタクシーを半日貸し切って、親子の曾遊の地というか、逢坂さんが一番思い出深いという浅草近辺、また時代小説を用意していた逢坂さんが題材に選びたいと決めていた北区の誰ぞ(忘れました)の関係する土地をカメラマン(お喋りだが、写真がからきし下手な社員カメラマン)を連れて、歩いたというか走ったことがありましたっけ。
浅草に「ヨシカミ」という有名な洋食屋があり、小さいころ逢坂さんは、ここに連れてきてもらうのが無上の喜びだったとかで、親子で久しぶりに食事をとってもらいました。
島倉千代子の「東京だよ、おっ母さん」では、浅草は「お祭りみたいに賑やかね」と歌っています。また最近は賑わいが戻ってきたようですが、そのころは寂れている印象でした。東京の田舎という感じでしたね。
以前国際劇場があった大通りに出たとき、「おーい、中!」と呼びかける中年男性がいました。逢坂さんの中高の同級生でした。逢坂さんは、日本で一番大勢東大に入る開成学園の出身なのです。浅草は開成の勢力範囲で、商売人の子弟などが通った、元は「地縁」的な学校だったんですね。
中さんが長生きしたのは、そもそも中さんの身体がそういうふうに出来ていたと考えるしかないのですが、一つ、息子たちの父親との距離の取り方が絶妙だったということも寄与していたかもしれません。
ある文学賞のパーティのときです。珍しく中さんが出席していました。どなたか縁の方が受賞でもしたのでしょう。パーティ半ばで高齢の中さんがお帰りになるというときに、逢坂さんを見つけて声を掛けました。その日は、どうも中さんはお一人で見えられていたと思います。息子としては、せめて見送りくらいしたほうがいいのではと心配したのです。逢坂さんは「いいんだよ、年寄りを甘やかしちゃいけないからね」と薄情なセリフを吐きます。しかし、そうやってなんでも自分でやることで心身がしゃきっとして健康が保てていたのかもしれません。年寄りには少し冷たくしたほうが長生きするということでしょうか。
今から何年前のことか、15年は前のことだと思いますが、ある日、中さんから連絡が入り、いついつに新潮社を訪問したいというのです。理由を尋ねると、実は高齢で一家を構えてゆくのがたいへんになってきたので、三重県津市に在住の長男のところに身を寄せることになった、ついては別れの挨拶がしたいと。
新潮社訪問の当日は、中さんは上田さんと一緒に見えられて、私や装丁部の高橋君、「小説新潮」のアルバイトで中さんの絵をよく貰いに行っていた、田中亮二君などと一緒に記念写真に納まりました。その日が中さんのお姿の見納めになったわけです。
それからほどなくして、津市に向かった中さん。一緒に長年住んだ上田さんは、大阪の実家に戻ったと聞きましたが、身体が動けるうちは上田さんに会いたくて、大阪まで出かけていたとも噂で聞いたことがあります。
津に移られてからも年賀状も多分七、八年まえくらいまでは交換していたように思います。一目で中さんの字だと分かる、ちょっと震え気味の文字で、「元気でやっております」というような一言が書き添えてありました。
中さんから貰ったお盆が私の家にあります。どういうタイミングでいただいたのか忘れてしまったのですが、女房に中さんの訃報を伝えると、女房が「あのお盆に冥福を祈っておくよ」と電話で言いました。私は現在、京都に単身赴任中で、お盆とはまだ対面していません。今度、東京に戻ったときに、私も中さんのお盆へ向かって、長年の厚誼<こうぎ>に感謝したいと思っています。