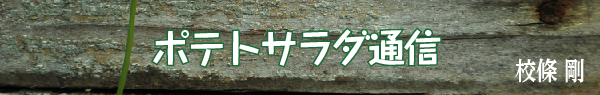ポテトサラダ通信 10
『作家という病』の刊行余波
校條 剛
7月に講談社現代新書から『作家という病』という題で新著を刊行しました。これまで河出書房新社、ポプラ社、講談社と全部単行本だったので、部数は知れたものでしたが、さすが新書は基本全国にバラまくのでそれなりの部数になりました。
私は自分の目では見ていないのですが、東京神保町の三省堂書店本店では、入り口近くの平台にピラミッドのように堆<うずたか>く拙著を積み上げていただいたようで感謝に堪えません。飛ぶように売れたとは聞いていませんので、たくさん仕入れていただいた三省堂さんにご迷惑をかけたのではとそれが気がかりです。
今回は、前著の『ザ・流行作家』よりも内容が一般向きだったためか、知人、友人が偶然に書店で目にして買い求めてくれたケースが多かったようです。いちいち報告が入るから分かるのですが、高校の同級生の一人は、「買ったはいいが、詰まらなかったら怒るぞ」とメールしてくる始末。
しかし、今回はまったくの他人事のような気分で発売からの日々を過ごしていました。前著のときは、都内の主要書店を回って売り込みにこれ務めたものでしたが、今回は京都にいるのを幸い(?)、プロモーションは一切しないで自然の流れに任せていました。前著のときは、ほとんど「無職」状態で時間がたっぷりあったのですが、今は京都に単身赴任して、大学の仕事に勤しんでいるので、時間も気持も余裕がありません。
一度、ラジオの出演と共同通信の取材のために出向いたのが唯一のプロモーションでしょうか。
ラジオは文化放送の浜美枝さんの番組で、タイトルがいつになっても覚えられないのですが、日曜日の10時半からの放送でした。もう終わってしまったので、このブログで予告などは意味ないですし、私自身も京都にいるため聴けないでいましたが、東京にいる女房の感想は「合格」だったのでほっとしました。
あらためて聴きたくなかった理由の一つに、最後の質問で「あなたの想い出の味は?」という、その答えが自分で納得がいかなかったことがありました。直前にそういう質問をしますよとは聞いていたのですが、ほんの15分ほどまえなので適切な解答を思いつかなかったのです。
私の答えは「東京・赤坂の日本一高額と言われている鰻料理の『重箱』のうなぎ」だったのですが、浜美枝さんが「私たちにはとても高嶺の花」みたいに返されて、まあ、浜さんなら行ける経済力をお持ちだろうけれど、庶民派なのでそうも言えないだろうな、なんて考えていました。
私も新潮社にいたころもっぱら接待に使っていたわけで、社用族として随分と通った店です。日本一高い鰻店といっても、実は銀座などの有名和食店に比べれば、むしろ安い料金でしたので、社用といっても莫大なお金をつぎ込んだわけではありません。むしろ、社用で使う店の中では安いほうだったことはここで断わっておきます。
それはともかく、私が自分で驚いたというか呆れたのは、自分の歴史を振り返ってみてもすぐに「あれだ」と思い浮かべられる味がないということなのです。人一倍食いしん坊で、今も夕方になって空腹感を覚えると不機嫌になっている自分を発見するほどなのに、過去の食事のなかで煌めいている瞬間がすぐに出てこないというのはなんなんだろうと自分の味覚に対して大いなる不信感が芽生えてしまいました。
そもそも、女房の料理は措いておくとして、母親のつくってくれた料理の一つや二つ言えないと母親に対して申し訳ないではありませんか。
浜美枝さんのこの番組ではゲストに対して必ずこの質問を出すそうで、あとで分かったのは、番組のスポンサーがJAだったのですね。
帰りの京都への新幹線のなかでやっと番組にふさわしかったであろう味を思い出しました。
新潮社の編集者時代に、新入社員のころから残業のたびに通った洋食屋に「せがわ」という洋食店がありました。地下鉄東西線の神楽坂駅の飯田橋よりの出口から出てすぐのところにあった、カウンター主体の店です。通い出して十年かあるいはもう少しでしたか、突然、閉店してしまい、厨房に立っていた大男の二人のシェフの行方も分からず、「せがわ」の味は永遠に私の前から去っていったのです。
この店で絶品だったのは「タンシチュウ」。生まれて初めてこの料理を食べたのもここです。デミグラスソースを使った普通の調理法ではなくて、特別のソースが掛かっていました。ちょっと口では説明ができません。タンシチュウのほかにも「舌平目のフライ」もよく食べました。「ホタテ貝柱のフライ」もうまかったですね。そうそう、付け合わせに「コンビネーション・サラダ」も頼みました。ただ、料金が随分と張ってしまうので、サラダはミニサラダにすることもありましたっけ。
いつも仕事中の夕食として訪れるので、ビールを飲もうかどうしようかと、それこそハムレットのように悩んだものです。ビールは小瓶が用意されていたので、まことに都合がよかったんです。
誘惑に負けてビールも仕込んで編集部に戻ると「進行係」の森定さんから、「飲んできたのかい」と非難がましく言われるのが多少辛かったですね。私の顔はビール小瓶でも真っ赤になるのです。その森定さんもあっけなく亡くなってしまいました。往時茫々とはこのことですか。