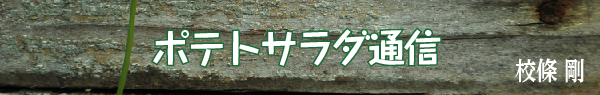ポテトサラダ通信 80
新保博久氏からの寄稿『祝祭のあと』
校條剛
私の名前をネットで検索していただくと、画像や記事などもろもろの情報が並びますが、かれこれ15年程まえからWikipediaも作成されています。誰が作ってくれたのかまったく分かりませんが、当初よりwikiの管理者より「第三者からの出典が示されていない」とか「特筆するべき人物とは思えない」など不快な注意書きが貼られています。特に「日本推理サスペンス大賞を創設した」という言明には、第三者の証言などの参考文献を示せということらしいです。しかし、私がペンネームを作ってさし上げた高村薫さんなどがエッセイで述べていることもないようなので、私が中心になって創設したという証言は、知る限りは探し出せません。そこで、当時の予選委員であったミステリー評論家の新保博久氏に一文を投稿してもらうことにしました。本文中に書かれていますが、「推サス大賞(名称を略しています)」の予選は一次、二次ともに同じ書評家メンバーで行なわれました。関口苑生、井家上隆幸、新保博久、長谷部史親、香山二三郎の五氏でした。このうち、現在存命なのは新保氏一人というわけです。新保氏はまだまだ長生きしそうなので急ぐ必要はなかったのですが、新保氏ではなく、私のほうに何かが起こることだってありますので、この時点で寄稿してもらったわけです。ちょっと長めではありますが、お読みくだされば幸いです。なお、日本推理サスペンス大賞創設の裏話はこの「ポテトサラダ」ブログで以前書いていますので、そちらを参照ください。警察の捜査でよく言われる「当事者にしか知りえない証言」が確認出来るはずです。
→「日本推理サスペンス大賞」設立秘話
祝祭のあと 新保博久
2025年は何という年だったやら! 6月に関口苑生氏、9月に香山二三郎氏と、ミステリを中心にやってきた書評家二人が、70歳前後で相次いで亡くなった。現代では夭折のうちに入るだろう。会社勤めをせずに、書評やら文庫解説、新人賞の下読みやら文芸業界の雑用だけで生計を立てていた珍しい存在として、あと一人加えて「書評三銃士」と名づけたのは北上次郎氏(「書評稼業四十年」第10回、『ハヤカワミステリマガジン』2017年11月号)だ。北上氏は書評の先達だが、大学卒業後いくつかの会社を渡り歩いているし(どれも長続きしなかったが)、最後には自身で興した本の雑誌社の社長に落ち着いた。会社勤めをしなかったという三銃士の資格には欠ける。三銃士の関口・香山のあと一人は、かく言う私なんだそうだ。
歩く不摂生のような関口氏よりは長生きするだろうと決め込んでいたが、まさか香山氏にまで置いて行かれるとは思わなかった。しかし正直なところ悼む気持より羨ましい想いも禁じ得ない。書評家にとって、まさかここまで生きづらい時代になるとは予想もつかなかった。終わりの見えない出版氷河期にあって、これからは苦汁をなめ続けなくても済むのだから。
業界のかたがたには釈迦に説法だろうが、ネット社会になって紙の出版物は危機にさらされ続けている。あらゆる企業が雑誌など紙媒体に広告収入をもたらさなくなった。媒体が滅びればライターには稼ぎ先がない。また、通販の急成長によって書店が立ち行かなくなってきた。店舗数だけでなく、生き残った書店の売場も縮小しており、正確な数字を把握しないが、売場面積は十年以前から半減しているだろう。配本先が減れば出版部数も削られるわけで、小説家も大変だが、そのお余りを頂戴してきた私どもにとっても他人事ではない。
そこで「昔はよかった」という話になるわけで、たまたま手許にある『公募ガイド』1997年8月号別冊「これで賞はもらった!」を見ると、推理ミステリ系として江戸川乱歩賞・横溝正史賞・サントリーミステリー大賞と挙げられているのが、軒並み賞金1000万円+印税と好景気だった往年の状況を窺わせる。これらの賞にはそれぞれ、フジテレビ・東京放送・朝日放送とTV局がスポンサーについていればこその高額賞金で、そうした後ろ盾を持たない日本ミステリー文学大賞新人賞でさえ賞金500万円と気張っている。この別冊は「公募まるごと年鑑」を謳っているのに、鮎川哲也賞だけ無視された形なのは、印税のみで賞金がないせいかもしれない。
やはり賞金1000万円だった日本推理サスペンス大賞(以下「推サス賞」と略記する)が挙げられていないのは、1994年に第7回で終了しているからだ。主催の日本テレビ放送網が手を引いたため消滅したが、賞名の冠になっている「日本」は日本テレビの謂だろう。協力出版社だった新潮社が後継的に自前で設けた新潮ミステリー倶楽部賞は、賞金額では100万円と一気に後退した。惰性で続けているような新人賞もなくはない中で、推サス賞はわずか7回で撤退したというのは潔い感じも受ける。1988年の第1回は大賞受賞作なし、優秀作に甘んじた乃南アサは直木賞を受賞するまで8年ほど雌伏を余儀なくされた印象だが、第2回の宮部みゆき、第3回の髙村薫と、受賞からたちまち脚光を浴びて、現在に続く女性作家の興隆期を牽引し、打率が高いといわれたものだ。
前記『公募ガイド』別冊では、直木賞受賞の余光だろうが乃南氏が巻頭インタビューに登場している。それによると、推サス賞優秀作『幸福な朝食』は「締切が6月。発表が8月。すぐに出版されて、テレビドラマ化の制作発表、放映がありました。もともと日本テレビの開局35周年を記念した賞だったので、1年間のうちに企画から放映まで終えなければならないという制約があったんです」という。
おお、そうだったのか。それと教えられていてもすぐ忘れかねないが、7回を通じてすべて、応募作を下読みして粗選りする予選委員を拝命していたから、心得ていても良さそうなものだった。当時の新潮社は日本ミステリの出版にあまり強くなく、書評家では比較的出入りしていた関口苑生氏が『小説新潮』の校條剛次長から予選会の人選を一任された。結果、関口氏当人のほか選ばれたのが井家上隆幸・香山二三郎・長谷部史親の諸氏に私の計5人である。他の4人より20歳ほど年上で最年長の井家上氏を除いて、全員ワセダ・ミステリクラブ出身の同時期在籍組である。まるで学閥だが、ひと世代前の重鎮を除けば、書評家連中など当時はそれくらいしかいなかったからに過ぎない。
推サス賞の予選会は仲間内らしく狎れ合う、という感じではなく、意見を異にする相手を劇しく糾弾するような局面もあった。だから第2回で、宮部みゆき『魔術はささやく』に予選委員全員が揃ってA評価をつけた時は、陪席していた新潮社や日テレ社員から嘆声が上がったほどだ(その時点では予選委員以外の誰も読んでいなかった筈)。これは探偵小説専門誌『幻影城』のファンクラブで雑誌消滅後も存続していた「怪の会」にいた長谷部氏が、やはり会員の宮部氏に推サス賞への挑戦を勧めたと仄聞するのが間違いなければ、予選委員に長谷部氏がいなかったら宮部氏が応募することもなかったかもしれない。
それに先立つ第1回の予選委員会では、高場詩朗「あしながおじさん殺人事件」が最も高評価だったと記憶するが、予選ではそれより支持が少なかった『幸福な朝食』を前にして本選では敗退している。「あしながおじさん殺人事件」はその後『神戸舞小浜殺人事件』と改題のうえ天山ノベルスで刊行されたが、作者両氏の活躍ぶりを比較しても本選委員のほうが予選委員より目が高かったというべきだろう。
『魔術はささやく』はたまたま私が最初に読む番が回ってきて、「ああこれで受賞は決まりだな」と感じたものだ。予選委員が5人いれば、いきなり受賞作を引き当てる確率は20%だから、ほかのひとが推してきたものを読む二次予選よりも先に、事前情報なしに授賞の手ごたえを感じることは少なく、いま咄嗟に思い出す同様の例は江戸川乱歩賞の高野和明『13階段』(2001年)ぐらいしかない。そのように乱歩賞など他の推理小説新人賞の予選もいくつか仰せつかってきたが、推サス賞はいろいろな意味で風変わりだった。
すべての応募作も最低2人が目を通すのは、どの賞もだいたい同じだが、そのためにコピーして副本を作るところ、全部をコピーするのは無駄だと考えられたのか(実際そうなのだが)、1部しかない応募原稿を予選委員が回読していた。業者の配送に任せるのは万一紛失事故があってはと不安なので、新潮社の社員みずから委員宅を襲って読み終わった分を回収し、ただちに次の委員に届けるというシステムで、だから読了期限を1日でも違えるわけにいかず、これが一番サスペンスフルだったかな。そのころ私が住んでいたのは、校條さんのご実家の近くだったのは単なる偶然で、関係のないことだが、中央線荻窪駅からも西武新宿線井荻駅からも中途半端に遠いその住まいへ、まだ若手だった私市さんらが社用車で乗りつけ、応募作の詰まった段ボール箱をあわただしく取り替えって行ったりした。応募作のコピーを詰めた段ボール箱を委員各自、読み終えたら返送するという他の賞とはやり方が違っただけに印象深い。
出版社主催の賞だったら受賞作の決定から日を置いて、文芸や報道関係者を多数招いて大規模なパーティが催されるところ、日本テレビ主催だからそんなにカネは出せないとでも考えられたように、第1回はともかく、第2回以降、そうした催しがなかった点も特異だ。本選考が赤坂プリンスホテルで行なわれているあいだ、誰に決まっても直ちに受賞者の記者会見に臨めるように、最終候補の作者全員が、赤坂プリンスホテル界隈で待機していなければならなかったのだ。受賞できればともかく、待ちぼうけに終わった候補者はさぞ居心地が悪かっただろう。
予選委員は別に付き合って待つ義務はなかったのだが、まあこれも歴史に立ち合う瞬間なのだからと例年、新潮社に集って決定のニュースを待っていたものだ。そのころはみんな忙しくて、しかし常に読むべき本を何冊も控えている状態だったから、長い待ち時間も別に苦痛ではなかった。何が見逃せない作品なのか、同業者同士で情報交換できる貴重な機会でもあった。ある年、新潮社内の講堂のようなところで、決定を待ちながら読んでいたのが花村萬月『ブルース』だったから、刊行年を調べてみると1992年のことである。近くすごい新人がデビューするらしいという噂を耳にしたのもそんな席だったような気がするが、やがて刊行されたのは京極夏彦『姑獲鳥の夏』で、1994年だったわけだ。いつもミステリ界の話題をさらう作品に事欠かなかった気がして、あの期間は書評家たちにとっても祝祭的時間だった印象を残す。
祝祭には当然終わりがある。しばらく後、香山氏と関口氏は江戸川乱歩賞の予選に移っていったように憶う。井家上・長谷部両氏と私は、日本推理作家協会賞の評論その他の部門の予選委員として顔を合わせたのが、2005年度~10年度と6年間に及んでいる。
井家上氏は2018年1月、長谷部氏も2022年4月に亡くなった。2018年は私が東京を引き払って京都に移住した年で、厖大な蔵書を抱えての暴挙に心身ともに打ちのめされていて、あまり記憶にない。年長の井家上氏が最初に鬼籍に入るのは驚くこともなく、気がつくといつの間にか亡くなっていたという印象である。現在かえりみれば、推サス賞の予選委員でも私が最後の生き残りになってしまった。だから、どうだということもない。だが、人はいつか死ぬという当たり前の事実を噛みしめ、遠からず私も仲間入りするだろうと感じる頻度は上がっているようだ。