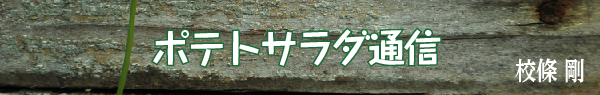ポテトサラダ通信 51
早稲田が殺した
校條 剛
とうとう書いてくれました。あの時代の最悪最低の早稲田大学の実体を、早稲田出身で元朝日新聞記者の樋田毅(ヒダ・ツヨシ)さんが、『彼は早稲田で死んだ』(文藝春秋)という単行本で詳しく明らかにしてくれました。
「早稲田で死んだ」のは、川口大三郎君という、当時二年生の学生で、革マルの数人に殴る蹴るの暴行を受けて亡くなったのですが、正確には大学そのものに殺されたのです。私もそのときは授業中の教室にいたと記憶します。1972年11月のことで、私は翌年の春に卒業を控えた4年生でした。出版社の新潮社に就職が決まっていて、あとは卒論を提出するだけという状況下にいました。
この本の著者は川口君の事件のときは一年生、私より三年下なので、大学での時間はほとんどダブっていないのですが、革マルという一セクトに学生時代を台無しにされたことには変わりがありません。
私が入学したのは1969年、東大安田講堂事件の後始末で東大の入試が戦争中を除いて史上初めて中止された年でした。「みせしめ」のためでしょうが、受験生にはまったく責任がないのに、紛争当事者と同罪にされたのです。そのことは、このブログ・シリーズの別の回に書いていますので、そちらをお読み下されば幸いです。
私の場合、樋田氏の時期よりも酷かったのは、入学して間もない5月の連休明け(多分)に、全学集会と称する革マル主導の学生大会が文学部の広い教室で開かれて、まえのほうに陣取ったヘルメット姿の革マルの連中の「異議なし!」の連呼とともに(同級生の榎本君によると、不正な投票も行なわれたと言いますが、記憶にありません)、たちまち「全学スト」が宣言されて、バリケードがキャンパス入口に積み上げられたのです。大学当局は、すぐに「ロックアウト」宣言をかまして、学生の立ち入りを禁止します。革マル自治会が入れないのはもちろんですが一般学生も閉め出しです。ロックアウトが解けたのは、なんと四ヶ月経った9月の半ばになってからでした。
あの暗黒の時代を過ごした一人として、終生赦せないのは、「革マル」集団だけではなく、いやそれよりも正常化に努力しなかった「早稲田大学当局」に対してです。長年、あの時代の文学部がどれほど酷い状態だったかを告発したい気持ちがありましたが、何分、樋田さんほど紛争に深入りしていたわけではなかったのと、記憶もかなり抜け落ちているので、誰か有志が書いてくれるのを待っていました。
いや、それよりも大学の四年間を台無しにしてくれた仇敵のことを思い出すだけで、私の身体中の血液が憤怒のために盛り上がって、喉が詰まって言葉が出なくなるのです。想像してみてください、憤激による興奮のために言葉を失ってしまう状態を。しかも、卒業してからすでに48年も経っているのにですよ。
学生時代にいい思い出しかないOBたちは、野球の早慶戦、ラグビーの早明戦、酒と異性との付き合い、部活動とアルバイトなどで過ごした楽しい思い出ばかり蘇るのでしょうが、どっこい「暗黒の70年代」に早稲田にいた私にはいい思い出は一つとしてありません。
私が早稲田第一文学部に入学した1969年から、樋田さんが卒業した1975年くらいまでは、早稲田の各学部の自治会は革マルという一つの左翼集団に支配されており、大学もそれを認めているという状態でした。特に革マルが強かったのは、地理的に独立した敷地にあった文学部でした(理工学部も独立していますが、本部から遠すぎるのと、文学部は思想的な背景が色濃いという内容的な特徴がありますので)。
早稲田という大学の特徴であるかもしれませんが、文学部のキャンパスほど人間味の薄い殺風景な場所は少ないでしょう。学生が教授を中心にして、芝生の絨毯上で円陣をつくり、将来の希望を語り合うなどという絵のような情景をキャンパスに求めている人には、コンクリートむき出しの砂漠のような空間は非人間的としか形容できません。
一左翼セクトの革マルが圧倒的に上回る人数の全学生を恐喝し、暴力を加え、授業を妨害し、自治会費と学園祭の入場料をセクトの資金としていました(私は早稲田祭のときに、学内に一度も立ち入ったことがありません。現役の学生なのに、百円だかの入場料が課されるからです。自分の大学なのに入場料ですよ!)。それらの悪行を受動的だったとはいえ、有言無言に認めてきたのは大学の総長と教授会、職員たちです。
早稲田はある意味ではユートピア世界を追い求めた存在だったのでしょう。いや、ユートピアなんてきれい事ではなく、単に無責任だっただけなのです。大学の経営上の問題ですら、日大に見るごとく理事長一存で差配することもできません。最も権力を持っているのは、理事長や理事会ではなく、各学部の教授会です。
多くの私立大学では、世襲の理事長が権力を恣に振るって、教授会などは理事会の決定を追認するだけの存在ですが、早稲田のような伝統ある「一流大学」では、先ほども述べたように教授会が最大の権威を持つという「理想的な」組織を誇っていたのです。経営的な利益優先方針よりも、人間育成とか学問研究の自由とかを上位に置こうという姿勢があるわけでしょうか。かっこよく言えば、早稲田は「自由」という概念を大事にしてきた大学でした。学生を束縛しないと同時に、教員も自由気ままに振る舞うという意味です。学内に国家権力、つまり警察が入りこむことが教授たちにとっても、絶対に避けたいという事態だったのです。
しかし、学生運動が盛んになるにつれ、それが裏目に出ます。「学生の自治」「国家権力の大学内侵入排除」などという言葉の上の理想に囚われてしまったのです。
文学部のキャンパスを一歩出れば、誰もが法律の網の中で行動を支配されます。路上で人を殴ったり、持ち物を奪えばすぐに通報され、警察官がやってきて逮捕されるでしょう。
しかし、ひとたび早稲田文学部の構内に入ると、そこに広がっているのは無法地帯としか言いようのないブラックな世界なのです。自分たちと敵対していると見るや、ヘルメットを被った革マルの学生たちは手には角材や鉄パイプを持ち、相手を殺さないまでも、一生不具者になるほどメッタ打ちにするのです。そんな卑怯な暴力行為が日常的に行なわれていたのに、大学側はほとんど手を打たず、あいかわらず革マルを温存していました。
現在のミャンマーに見るような暴力支配の実際は、樋田氏の『彼は早稲田で死んだ』に詳しく書かれていますので、そちらをお読み下さい。
私自身はクラス内での対立であわや殴り合いという局面はあったものの、暴力自体を受けることはありませんでした。ただひたすら苦痛だったのは、授業が受けられないということ以上に、本来憲法のもとに自由であるはずの一市民が独裁勢力に支配されていることでした。校舎に囲まれた中庭では、立て看板が立ち並び、連日マイクのアジ演説を聴かされる苦痛たるや耐えがたいものがあったのです。
私がいま出来ることは、大学当局に恨み辛みを述べることではないでしょう。多分、いまだに早稲田大学の教職員の皆さんは、1970年代の諸相はもう過ぎたことで再び起こることはないと楽観していると想像します。その勘違いを正しておきたいと思います。
当時流行った言葉使いで言いますと、大学当局は「総括」していないのです。大学が正常化したときに、それまでの紛争の実態を振り返り、どこで間違ってしまったのかを反省することをしていないと思えるのです。
どうして、教授会は一左翼組織「革マル」の支配を許してしまったのか、その原因を突き止めて、将来、再びこうした事態が出来するまえに手を打つべきなのです。
次の二点について、私の主張を述べたいと思います。
1 大学の役目とは何か?
2 組織を正常に運営するにはどうしたらいいのか?
大学の役目とは? それは、学生が何の目的で入ってくるかで決まります。学生が求める目的は微妙に異なっているでしょうが、一つ否定しようもなく共通していることは、「授業」というものの存在です。授業が行なわれることは当たり前の前提であり、授業のない大学なんてものはありません。大学での経費は授業料と呼ばれるように、学生は授業を受けるために入学するのです。昨今のように、それが対面ではなく、オンラインになったところで、授業の持つ意味は変わりません。
私の大雑把な計算では、私が早稲田にいて受けた授業時間数は四年分の半分、二年分ほどしかなかったでしょう。私は四年制大学の卒業証書を得て、学士を名乗っていますが、実は短大卒なのだと言ったほうが正直というものです。私の四年分の授業料は、授業に対してではなく、一枚の卒業証書を買い取るために支払ったのです。
次に「大学組織」を考えるときに、学生の自治という点に絞って述べましょう。1970年代のような悲惨な状態に陥らないようにするためには、学生の権限を限定的にすることが大事であると思います。大学内は「治外法権であるべきだ」とか「学生は受動的であるばかりではいけない、能動的に学内の自治を模索しなければならない」とかの理想主義は捨てた方がいいのです。いや自治というもの議論し、模擬的な自治を体験することは意味があるかもしれませんが、学生に与えられる環境はあくまでも、模擬的なそれであるべきなのです。そして、暴力が入り込んだときには、暴力排除装置(即ち警察)をためらいなく投入することです。しかし、警察を導入するまえに、大学当局は、断固とした姿勢を示し、警告を発しておくのは当然でしょう。
再度、言います。理想主義は危険です。人間の自由と、無制限に自治権を与えることとは同義ではありません。一定の制約があってこそ、初めて人は自由を謳歌できるのだということを私は声高に言いたいのです。