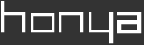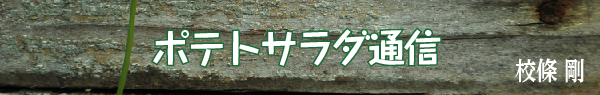ポテトサラダ通信 79
今頃読んだ『ノルウェイの森』 その2
校條剛
村上春樹は『ノルウェイの森』について、インタビューで「この小説を私の自伝的な部分の多い作品と考える読者が多いようだが、それは違っている」というように述べているので、私が前回指摘したような大学でのあれこれは無駄な言いがかりと反論されかねませんが、大学紛争時の様相は、その時期同じ空気を吸っていた私には、概ね事実と思えます。社会的な背景はフィクションではなく、事実なので私の意見は間違っていないと考えるのです。
もちろん、若干小説に都合がいいように変えている部分はあるでしょう。例えば、小林緑という最終的にワタナベの恋人になる奇矯な言動の女子学生とは、授業が重なっていたので知り合うわけですが、その授業がごく平穏に続いて開かれているというような「正常化」した風景には違和感があります。小説の都合から言えば、授業は正常化していなければならなかったのでしょう。
私がこの小説を読んで一番驚いたのは、「女性と寝る」「女性とする」エピソードが何度も無数といっていいほど出てくることでした。ラスト近く、京都の山奥の特殊な施設で病気の直子の面倒を見てくれていた、かなり年上のレイコさんとセックスしてしまうのは、これはやりすぎでしょう。この部分、作者は立ち止まって、考えたはずですが、これしか落とし所がないと決めたのでしょう。しかし、直子との純粋性に満ちた絆がほどけてしまう気がしました。
直子がこの世から去ったあとの、ワタナベが意識を失った人のように放浪するときの、どん底の悲しみを描く、直前のエピソードが嘘くさく感じられていた、あの感覚は正しかったのだなと納得してしまうのです。ワタナベはどうして直子に執着していたのかという疑問がいつまでも残ります。
普通の性行為ならまだしも、女性の手で「してもらう」(風俗で言う手コキ)が一度ならず、私の記憶では二回出てきます。最大のヒロイン直子だけではなく、小林緑にもやってもらっています。
評論家のなかには、「性」=生きることと捉え、何人かの死(その最大のものは直子の死)と対比されていると分析している人もいますが、私には単に「射精快楽者」としか思えません。
こうしたエピソードに驚いているのは、私だけではありません。ネットで検索すると、この小説を「気持ち悪い」と感じた読者が非常に多いのだと知りました。とくに女性読者には評判が悪いのではと推測します。
読者の投稿のなかで、一番納得したのは、「手コキ」などを「性描写」という綺麗な言葉で説明するのではなく、「下ネタ」という表現でこき下ろしたものでした。確かに、この小説で描かれているのは、性行為などというものではなくて、下ネタの類ですよね。
私個人は下ネタが嫌いなわけではありませんが、小説などではちょっと気取ってみたいと思うのです。やはり、カズオ・イシグロがノーベル賞を貰い、村上氏が取れなかったのは当然かなと、こういう部分でも感じますね。
それにしても、外国でもこの小説がかなり受けているというのは、不思議な現象で、私には理解が出来ません。
ただ、この小説を読んでいて、感心するところが多かったのは事実です。私も作家の端くれですから、実作者として「なるほど」「ここはうまいな」という箇所は随所にありました。男性、女性を問わず、その人物の性格を際立たせる技術はやはりなかなかのレベルだと思います。などと、偉そうに言うことはないのですが、結構感心して読んだのです。
とくに感心したのは、直子という複雑な女性の捕まえ方です。速断で言えば、統合失調症を患っているとしか思えませんが、この病気の特徴を、どうしてここまで村上氏が理解しているのかと。手コキはともかくこの複雑な女性をここまで深く描けるのは、やはり一流の腕前だと言うほかはありません。
直子は結局、自死するのですが(今さらネタバレはいいですよね?)、自死のまえに明るく立ち直ったように見え、十分に周囲を安心させて、しかも死ぬ準備は怠りなく、首を吊るのです。
統合失調症は自死するケースの多い病気で、私は息子が同じ病気だったので、直子の自死に至る様々な曲折に頷けるものがありました。直子の不可解な行動の一つ一つが彼女の個性というより、脳の不具合から生じる「機能的な」反応であることが、私にはよく理解できるのです。
ただ、統合失調症という病態は、最後の最後に最悪の結末を見るまでは、健常者に本質が理解できないことは、この小説でも直子の自死という結果を見ることで分かります。健常者には、どれほどこの病気に関する資料本を読み漁り、医師の解説や経験者の証言を聞いていても、結局は本当の理解は難しいものなのです。
その極めて複雑な女性を描く村上氏の筆致は称賛されるべきもので、氏の身辺に同病の親しい知人あるいは家族がいたとしか思えないほどです。
村上作品について、さらに好意的な言辞を述べて締めたいと思います。初期作品に対してはともかく、近作には物書きの一員として、学ぶべき点が散見できます。
といっても、私が読んだのは『1Q84』の第一部と『騎士団長殺し』だけなのですが、とりわけ後者には感心して、思わず感嘆の声を発してしまうような部分がありました。リアリズムの小説にファンタジーを取り込む技術が抜群に上手いのです。村上氏自身も、その秘訣について自身で解説していますが、それも読んで大いに啓発されました。
それでも村上春樹の『騎士団長殺し』と、たとえばカズオ・イシグロの『私を離さないで』を読み比べてみると、イシグロがノーベル賞に値する作家であることは明らかでしょう。村上氏はやはりエンターテインメントの作家であり、社会問題への関心よりも、物語の起伏が優先されています。純文学としては「面白過ぎる」のだと考えます。村上作品がイシグロ作品よりも価値がないわけではなく、目指す世界が違うのです。ノーベル賞など、要らないんですよ。
けなして、ほめてこのパート2を終わりにします。