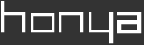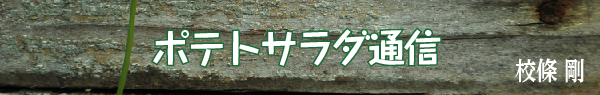ポテトサラダ通信 78
今頃読んだ『ノルウェイの森』
校條剛
ご存じ、「ノルウェイの森」。ビートルズの歌が先ですが、今や村上春樹の小説のほうが、少なくとも日本では知名度が高いでしょうか。
今年になって初めてこの小説を読んだと言えば、元文芸編集者たるものが、情けないと謗られそうですが、意識的につまり「嫌だったから」読まなかったのであって、怠慢からではないことは、これから説明します。
最初にビートルズの歌が先だと述べましたが、この小説のタイトルだけではなく、小説の冒頭にこの歌が登場することでも、この小説の最初の動機づけがビートルズの歌であったことは当然でしょう。
そのビートルズの歌詞は実はなかなか難解と言うか、韜晦的(とうかいてき)とするか、謎に包まれている印象があります。
ジョン・レノンがリード・ボーカルの曲ですから、基本詞も曲も彼が作っているのですが、詞の「So I lit a fire」という箇所はポール・マッカートニーのアイディアらしいです。「レノン・マッカートニー作品」と呼ばれるほとんどのビートルズ作品は、そのように共同制作されたのだといういい見本ですね。
さて、問題は「wood」なんですが、これを「木材」とではなく「森」と訳すかどうかなんですね。「森」の場合は「woods」と複数形にするのが一般的なようですから、ビートルズの「Norwegian Wood」を「ノルウェイの森」としていいかどうか。
ジョンの歌詞では、「森」とイメージさせる言葉を見つけることは困難です。ノルウェイの木、としても構わないような気がします。木というよりも、その木材をあしらった部屋だったのでしょう。
この「誤訳」問題は、丁寧に解説しているサイトがネットにありますので、私がこれ以上物知り顔で言い募る必要はないでしょう。
何冊もの翻訳がある村上氏が「wood」と「woods」を取り違えたということは考えられないので、ほぼ「誤訳」と知っていたのに、このタイトルのほうが小説の題名として相応しいと判断したものと思われます。だって、「ノルウェイの木(木材)」では、いささか艶に欠けるでしょう?
村上春樹は早稲田の文学部に1968年に入学しています。おそらく一浪です。私は一浪で翌1969年に同じ学部に入りました。実は私は現役のときにも合格していたので、そのまま入学手続きをとっていれば、村上氏と同期生になったはずです(彼は演劇学科ですが、私はフランス文学科です)。当時は浪人するのが当たり前の時代でしたし、学費の安い国公立に入ってほしいという両親の希望を実現するためにも、私は浪人を選んだわけです。1969年は東大入試が史上初めて中止された年で、入試があったとして東大を受けたかどうかは別として、結果的に早稲田に進学することになったのです。
1969年は、学生運動が一応の頂点を迎えた年でした。1960年の日米安保条約の自動延長が1970年に予定されていたために前年の69年から新左翼政治団体を中心に、激しい反対運動を起こしていたのです。68年から各派の全学連が首都圏を中心に大暴れしていて、歩道の敷石を剥がし、割って、その重いコンクリートの欠片を機動隊に投げつけていました。それに懲りた警察と行政が歩道から敷石を追放して、アスファルトに変えたのです。ある時代のこうしたトリヴィアは覚えている人が少なくなっているかもしれませんね。
私が入学した五月には自治会を支配していた革マルという左翼組織が全学ストを強行したのです。この決定をした学生大会に私も臨みましたが、前席を独占した革マルの連中とそのシンパが「異議なし」と反対の声などはまったく聞かずに決定してしまったわけです。票決などは行わずに、声の大きさだけの決定です。
すぐさまストライキに突入です。教室の椅子や机を持ち出し、入口に積み上げて、一般学生たちの出入りも拒絶しました。
私が学生運動を根本から嫌っていたのは、私という一個人を支配しようとする権力組織が存在したからで、学生運動家が嫌う国家権力と同等の権力でもって、一般学生を従わせようとしていたのです。私は以降、今日まで、他人を支配下におこうとするあらゆる勢力に対し、憎しみをもって対抗するようになります。独裁や人間の自由を奪うあらゆる行為に対してもの凄いアレルギーを覚えるのです。プーチン、習近平、キムジョンウン、トランプ、ネタニエフ、参政党……困った世界です。
さて、ストの続きですが、運営母体の大学当局は、それに対抗して大学封鎖の意味の「ロックアウト」で対抗します。
当時は、大学構内は警察の立ち入りを拒否する「大学自治」思想が蔓延していました。法治国日本のなかで治外法権は外国の大使館ぐらいではないでしょうか。一私大の内部に警察が立ち入ることを拒否するという考えが大学の教授会にも存在したのですが、私の考えではそれは「幻想」に過ぎません。
教授や職員が一政治団体の支配に抵抗するといっても、ゲバ棒を振っておおっぴらに暴力を行使する連中にどうやって立ち向かうのでしょうか。
入学してひと月も経たずに大学に通えなくなったために、我々一年生は同級生に馴染むこともほとんど出来ずに、秋の授業再開を待つことになります。
長々と当時の大学の混乱ぶりを説明していますが、私がほぼ同時期に早稲田文学部の在籍した村上春樹に同感できないのは、まさに彼がこの状況下にどういう考えを持っていたのかに関係してきます。
大学がロックアウトを解いたからといって、大学の機能、つまり多くは授業という形で示されるものは壊されたままでした。中庭では授業中にマイクを使ったアジ演説は果てることもなく続きます。授業妨害以外の何モノでもありませんが、教員職員ともに「やめろ」と命じることはありません。向こうはヤクザ同様に暴力を武器にしているので、所詮不可能なことなのです。授業のなかほどで、二人ほど「主義者」がやってきて、教師に「この授業の後半はクラス討論に変えてほしい」と半分命令のように告げます。これにも抵抗する教師はゼロだったと記憶しています。
私はそれでも教室の討論に加わり、「授業料を払っているからには、授業はあるべきだ」というような論を張り、のちに「授業再開派」と名付けられていたことを知りました。
私は授業がもの凄く好きだったわけではありません。授業が正常化していたら、すべての授業の予習復習をして、無欠席で過ごしただろうというわけではないのです。さぼることもあり、予習をしてこない日もありました。ただ、授業が行われていなければ、出席することが出来ないだけではなく、サボることも出来ないのです。それが、人間のというか学生の「自由」はそのあたりにあるのではないでしょうか。独裁者は常に我々の自由を奪いたがります。右翼であろうと、左翼であろうと変わりない真実です。
『ノルウェイの森』からそのあたりの記述を見てみましょう。
ヘルメットをかぶった二人の学生が、授業途中で入室してきます。彼ら(革マルとその周辺の者たち)が配るアジビラには「欺瞞的総長選挙を粉砕し」「あらたなる全学ストへと全力を結集し」「日帝=産学協同路線に鉄槌を加える」などと書かれています。
小説の主人公のワタナベはこのビラについて次のような感想を述べます。〈説は立派だったし、内容にとくに異論はなかったが、文章に説得力がなかった。信頼性もなければ、人の心を駆り立てる力もなかった。(中略)この連中の真の敵は国家権力ではなく想像力の欠如だろうと僕は思った。〉
褒めていえばクールでしょうが、上から目線というか、自分とは関係ないことと、つまり他人ごとと捉えています。「説は立派」とか「内容に異論はない」とはどういうことなのか。どこが立派なのだろうか、内容にも異論はない? このワタナベという男の政治的な信条とか、思想的な拠り所の表明は見られませんから、何を基準に異論はないのか分かりません。「想像力の欠如」という指摘も、笑うしかありません。何を気取っているんだと言いたくなります。想像力など、最初から持ち合わせていない連中であることは、ワタナベにも分かっているはずだからです。
村上春樹のような自分のことにしか興味がない人間は、結局は自分個人の快楽と失意しか描けないのでしょう。自分の人格について、自己分析は出来ているようで、以下の箇所で語っています。ただし、第三者の言葉によってですが。
〈「まあそうかもしれないな」と僕は言った。「たぶんそのせいで人にあまり好かれないんだろうね。昔からそうだな」
「それはね、あなたが人に好かれなくったってかまわないと思っているように見えるからよ。だからある種の人は頭にくるんじゃないかしら」と彼女は頬杖をつきながらもそもそした声で言った。〉
〈「俺とワタナベは似ているところがあるんだよ」と永沢さんは言った。「ワタナベも俺と同じように本質的には自分のことしか興味が持てない人間なんだよ。(中略)自分が何を考え、自分が何を感じ、自分がどう行動するか、そういうことにしか興味が持てないんだよ。だから自分と他人をきりはなしてものを考えることができる。(後略)」〉
まさに、そういうところが私との違いなのだと思います。私は「過剰共感・没入」タイプで、毎日の交通事故のニュースにさえ暗い気持ちになります。ウクライナ戦争のニュースでは、ロシアへの憎しみに身体が震えます。ですから、同じ時期に早稲田にいて、学園を支配し、机や椅子を破壊するような連中に憎悪を抱き、その連中と口論したあとに暗い気持ちを引きずってきたのです。こうして、当時のこと思い出しながら記している今も、不快さというより敗北感に似たマイナス感情が湧き出てきます。
以上が『ノルウェイの森』を読まなかった理由になりますが、しかし、読まないでいてどうして村上氏の小説に近づくのは危険だと分かったのでしょうか。それどころか、デビュー作の『風の歌を聴け』も忌避して読まなかったのですから、私のアンテナの感度が異常に鋭かったということなのでしょうか。いや、不思議です。
さて、この項も長くなり過ぎたようです。村上春樹『ノルウェイの森』については、さらに感想がありますので、次回「パート2」で続けて述べることにして、今回はここで筆を置きます。