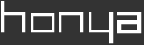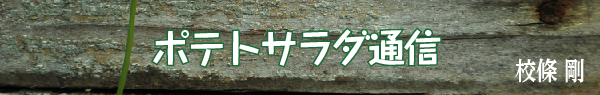ポテトサラダ通信 77
映画音楽について
校條剛
あの頃はどうしてラジオから映画音楽ばかり聴こえてきたのだろうか。あの頃といっても、いつのことだかお分かりにならないだろう。私が思い浮かべている時期は、私が中学高校生のころであるから、西暦では1962年から1968年あたりまでのことだろうか。1969年に一浪して大学に入学してからは、中波ラジオの深夜放送を聴いてはいたが、多分映画音楽の時代は終わっていた。
不思議なのは、小型ラジオを持っていた記憶がないのに、どうやって映画音楽を聴いていたかである。大学入学と同時にパイオニアのセパレート・ステレオ装置を買ってもらってからは、ヘッドフォンを付けて布団にもぐって深夜放送を聴きながら笑いこけていたりしたのだが、その時代にはラジオの番組内容は大きく変わっていたのである。
その謎は置くとして、中波ラジオから流れていた映画音楽のタイトルを思い出してみよう。これらは、すべてといっていいほど、映画のサウンドトラックであり、マントヴァーニ楽団などのカバー演奏ではない。
ティファニーで朝食を
シェーン(遥かなる山の呼び声)
鉄道員
ブーベの恋人
エデンの東
道
汚れなき悪戯(マルセリーノの歌)
太陽がいっぱい
風と共に去りぬ(タラのテーマ)
誇り高き男
刑事(アモーレ・ミオ)
栄光への脱出
旅情
真昼の決闘(ハイヌーン)
慕情
禁じられた遊び
アラモ
第三の男
ライムライト
このなかで現在、まったくといっていいほど聴かれなくなっているのが、「誇り高き男」であるが、おそらく映画そのものが忘れ去られているせいだろう。
私が映画の音楽に惹かれるのは、多分、メロディーのストーリー性にあるのだろう。映画そのものを観ていなくても、ドラマの内容が想像出来るように書かれているからなのではあるまいか。もちろん、曲想のはっきりした、歌謡性の高いメロディーを重視して作られていることが最大の理由ではあるだろう。
現在はテーマ曲をヒットさせてから、映画の公開に入るという手法がとられることはほとんどないが、パソコンやスマホで予告編を観ることが出来なかった当時としては、テーマ曲をヒットさせるという手法が広くとられていたわけである。
実はアルトサックスを少し吹けるのだが、得意な曲はミケランジェロ・アントニオーニ監督の「太陽はひとりぼっち」(原題「日蝕」)のテーマ曲である。この曲は最初か最後のクレジット・タイトルのときに流れるが、音楽に頼ることの少ない作風のアントニオーニは、映画本編の間に、このメロディーを流すことをまったくしていない。この切ないメロディーに誘われて「太陽はひとりぼっち」を観ると、アントニオーニ作品の傾向を知らなかった観客にははなはだ不評を蒙ったことだろう。いわゆる芸術映画であって、単なるメロドラマではないからだ。
アントニオーニと同時期に芸術映画を代表するイタリアの監督はフェデリコ・フェリーニだ。私はある時点までのフェリーニ映画をほとんど観ているが、後期作品の始めのころ、確か「女の都」「そして船は行く」「ジンジャーとフレッド」あたりを最後に新作を観なくなった。その理由はフェリーニ映画の音楽のすべてを担当していたニーノ・ロータが亡くなり、別の作曲家に変わってしまったからだ。ロータのメロディーが聴けなくなってからもしばらくは我慢して観ていたが、そのうちフェリーニの映画表現が空回りしていることに苦痛を覚えるようになった。そのとき、私ははっきりと悟ったのだ。「フェリーニの映画を観ていたのではなくて、ロータの音楽を聴いていたのだ」と。
岡田暁生氏は音楽学者で、中公新書で『オペラの運命』と『西洋音楽史』という素晴らしい本を出している。『オペラの運命』の最終章で〈こうした職人気質の作曲者たちは、二十世紀においてはオペラから離れて、映画の世界に移住していったのである。〉と。極めて卓見である。ロータは自分を映画音楽のプロと呼ばれることを嫌って、クラシックの作曲家であることを自負していた。管弦楽作品だけではなく、オペラ作品もある人なのである。岡田氏によると、ジュゼッペ・ヴェルディに比肩するような才能だそうだ。
それにしては、岡田氏の記述には間違いがある。ロータの映画作品を何作か挙げているが、その筆頭に「ひまわり」を置いている。ヴィットリオ・デシーカ作品で、音楽はアメリカのヘンリー・マンシーニである。「ティファニーで朝食を」などオードリー・ヘップバーンの映画のほとんどの音楽を担当していたメロディー・キングである。
それは蛇足として、クラシック作曲家が映画音楽の分野に進出して優れた仕事を提供してくれたおかげで、私はいまだに映画のメロディーを聴くことが多い。ニーノ・ロータ、モーリス・ジャール(「アラビアのロレンス」「ドクトル・ジバゴ」、それと西部劇作品の多い、ディミトリ―・ティオムキン(「ローハイド」「ハイ・ヌーン」)、ミクロス・ローザ(「ベンハー」)など未だに愛聴している。
「スター・ウォーズ」のテーマ曲は、リヒアルト・シュトラウスの「ツァラトストラはかく語りき」からヒントを得たことで有名だが、作曲者のジョン・ウィリアムスもやはりまえの時代に生まれていれば、クラシック作曲家になっていたことだろう。
映画音楽の時代は終わっていないが、21世紀にクラシック作曲家はどのような進路を見出すのだろうか。