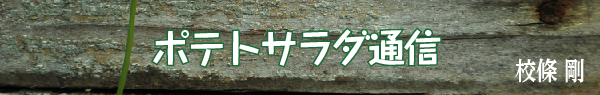ポテトサラダ通信 19
ダニエル・ダリューの100年
校條 剛
10月20日、フランスの女優ダニエル・ダリューの訃報記事は小さかった。しかも、通信社が流した顔写真はかなりの歳になってからのもので、若いころの美貌を想像するのは難しい。日本の新聞の扱いの余りの「無関心さ」は、記者の教養の貧しさからきているものだろう。念のため、ユーチューブでフランスのテレビ番組を検索してみたところ、どの局も過去の出演作の写真などを配して力をいれた追悼の番組にしている。フランスと日本、やはり彼我の差は大きいようだ。
日本でダニエル・ダリューの名前が大きかったのは、太平洋戦争のあとよりも前だったのかもしれない。若き日のダリュー作品ナンバーワンであろう「うたかたの恋」は、素材がオーストリア皇室のスキャンダルだというので、多分戦前は上映禁止、戦後解禁されたのだと思う。とすると、「禁男の家」や「背信」など戦前に上映されていた作品がかなりの評判になっていたはずだ。津村秀夫という朝日の記者(詩人の津村信夫の兄)は、戦前に発行された映画評論集のなかでダリューのことを「白痴美」と表現していた。ちょっと理解しづらい言葉だが、信じられないほどの美貌であることを表現したかったのか? あるいは、観客が口を開けて見とれるばかりの凄い美貌だと言いたいのか。いずれにせよ、白痴という言葉が公の場所から追放されしまった現在では使えない表現だろうな。
ダリューは1917年の5月の生まれなので、今年2017年に100歳の誕生日を迎えていた。私はフェイスブック上で100歳の長命を寿いだが、反応はほとんどなかった。今回の訃報の記事といい、5月のフェイスブックの反応といい、少なくとも日本人にとって、彼女の存在などどうでもいいことの一つになっていたわけだ。まあ、当たり前か。ジャンヌ・モローも先日亡くなったが、この人の場合の反響の大きさはダリューとは比べようがなかった。ジャンヌ・モローには「死刑台のエレベーター」にせよ「突然炎のごとく」にせよ、まだ人々の記憶に残る代表作がある。それに比べて、ダリューの場合、まず「赤と黒」つぎに「うたかたの恋」あたりがDVDで簡単に観られる作品だが、ともに普段から口にされるタイトルではない。80歳の時点で105本の出演作があったらしいが、ヴィヴィアン・リーのように「風と共に去りぬ」というウルトラヒット作があるわけではない。あるいは、オードリー・ヘップバーンの「ローマの休日」やイングリッド・バーグマン「カサブランカ」のような。確かに「うたかたの恋」は世界的なヒット作になり、ダリューの超絶的な美貌は、ハリウッドからの招聘を呼んだのだが、現代日本で「うたかたの恋」というと、カトリーヌ・ドヌーブのリメイク版を指す人さえいるかもしれない。ダリューの「超絶」美貌のまえでは、ドヌーブなど十人並みの女であることもそういう人たちは知らないのだ。
批評家が評価する主演作ということになると、マックス・オフュールスとの仕事になるだろうか。「Madame de …」(邦題『たそがれの女心」が嫌なので原題で)、「快楽」「輪舞」がそれらだが、あとのほうの二本はオムニバスであるから、全編ダリュー主演作というわけではない。私も彼女の100本に余る映画のほとんどは観ていないわけだから、偉そうなことは言えないが、私が知っているなかでは、ジュリアン・デュビビエ監督の「自殺への契約書」「奥様ご用心」あたりだろうか(両作とも原題は邦題とは別物)。最近DVDを手に入れたオータン=ララ作品「Occupe-toi d‘Amelie」という映画も本国では有名作のようで、しかも中年の美貌が輝くばかりの時期だから、この映画も外せないのかもしれないが、実はざっと中身を確かめただけで全部を観ていない(情けなや)。
彼女の美貌についてだが、ごく若いころの輝ける美しさ(まさに白痴美)、中年になってからの落ちついた深い美しさという二面を私は堪能してきた。こういう女優は実は珍しい。若いころは美しくても、年を重ねるにつれてだんだんと、あるいはいきなり仮面が剥がれたように美人とはほど遠い存在に変わってしまう女優が何人も思いつく。ヴィヴィアン・リーなど中年になってからの「ローマの哀愁」は容貌のあまりの衰えぶりに心が痛んだほどだ。
ダリューは違う。十代、二十代のころもいいが、三十代半ばから別種の美しさが備わってきたのである。特に美しいのは「赤と黒」のときだろう。この映画の製作年度は1954年、ダリュー37歳のときである。私は高校二年生だったと思うが、最初テレビでこの映画を観た。スタンダールの原作はもう読んでいたのだろうか。記憶にはないが、映画が先だったかもしれない。私は映画を観ているよりも、映画の音楽に浸っているのだとこの頃自分の映画鑑賞法について思いめぐらせることがあるのだが、この「赤と黒」の音楽が大好きなのだ。ルネ・クロエレックという作曲家で、監督のクロード・オータン=ララのお気にいりの人らしい。ダリューのレナール夫人が、なかなか自分の部屋にやってこないジュリアンを待ちきれず、忍び足でジュリアンの部屋に忍んでいくときのシーンの素晴らしさもさりながら、このときの音楽が耳から離れなくなった。高校のグラウンドでランニングさせられているときにも、この映画とダリューの美しさが頭から離れなかったくらいに入れ込んでしまったのである。有体に言えば、惚れてしまったのだ。私が年上の優しい女性が好みなんだと誤解してしまったのも、このレナール夫人=ダリューのことがあったからである。
大学生になって間もなくだったろうか、幸運にも「赤と黒」が映画館でリヴァイヴァル公開されることとなり、私は踊り上がるような気持ちで飛んでいった。ところが、愛してやまない上記のシーンがばっさりとなくなっていたのであった。私は輸入元の東和映画に電話を入れて、厳重に抗議をした。東和の説明ではフランスから送られてくるときに切られていたという説明だったが、上映時間が長い作品なので、こちらから時間指定をしたのではなかろうか。
映画も小説もそうなのだが、本筋のストーリーと関係のない部分にコンテンツの豊かさが隠されている。その部分をばっさりとそぎ落とされると、人間の肉体を描くのに、肉が描かれず、骸骨だけの骨格見本を見せられるようなものなのだ。ものを作ったり、書いたりする人はよくわかっている理屈だろう。
当時はまだヴィデオも登場していない時代である。だから映画館でのリヴァイヴァル上映を待つしかなかったのだが、初めてVHSで「赤と黒」が発売され(二本組)秋葉原で手に入れて帰ったときの喜びは人生何度もあるものではないと思う。
私は1990年にパリで実際のダニエル・ダリューを観ている。会っているわけではなく、姿と声とに間近に触れたのである。パリには一週間滞在し、その間、慶應大学からサヴァティカルで滞在していた木俣章氏にあちこち案内してもらったのだが、彼が「確かいま芝居に出ているよ」と教えてくれた。多分まだ存在すると思うが、「テアトル・アントワーヌ」という小さい劇場で演し物は非常に軽いコメディーだったような気がする。上演時間も短かった。主役を張っていたが、彼女以外の役者がどの程度のランクの人か分からない。席はいわゆるかぶりつきの正面まん前の列しか空いていなくて、止むなくというか、ダリューとの距離が一番近いのでかえって幸運だったのだが、その席で二日連続で通ったのである。そのうちどちらかの日には、女性だけの団体客が詰めかけていて、なんとなくフランスの田舎から貸し切りバスにでも乗って出てきた人たちかな、という印象を持った。
カーテンコールではバシバシ写真も撮った。真ん前の席でカメラを構えている小柄な東洋人の姿はさぞかし彼女の眼には奇異に映ったことだろう。本当は、バラの花束でも抱えて楽屋見舞いをしたかったが、そこまでの勇気はなかった。このときのダリューの年齢は73歳。いま思い出すとまだ若かったのだ。
ダニエル・ダリューは日仏合作の映画に一度出演するために来日している。原題は「長崎の台風」というのだが、日本題名は「忘れえぬ慕情」である。そう、日本の女優の岸惠子さんが監督のイヴ・シアンピと結びつく機縁となった映画である。
十七、八年まえになるだろうか岸さんの小説の担当者として岸邸に通って、二人だけで打ち合わせをしたり、食事をする機会が何度かあった。そのとき、私は何が何でもダリューと共演したときのエピソードを聞き出したかった。しかし、撮影中、ダリューとの交流が少なかったのだろうか、岸さんからダリューに関するエピソードがほとんど聞けなかった。その数少ない岸さんの証言で覚えているのは次のような発言だ。
「親切な人でした。私のフランス語の発音が頼りなかったので、フランス語のセリフをテープにいれてくれましたよ」
つまり、岸さんのフランス語の先生役を少ししてくれたらしいのだ。
その映画「長崎の台風」を私は池袋の文芸坐で初めて観た。この映画館で「岸惠子週間」を開催したときに、出演作の一本として上映されたのだ。そこでのダリューが日本の着物など着て、相手役のジャン・マレーにお銚子を持って酒を注ぐシーンもあったが、外国人が着物を着たときに外国人臭さが目立ってしまうことがよくあるように、ダリューが急に外国人ぽく映ってしまった。パリの舞台で観た彼女からは微塵もそんな感じを受けなかったのだから不思議なものだ。
パリにいたときの話に戻ると、パリの映画ポスター専門店と映画雑誌やスチルなどの専門店でダニエル・ダリュー関係のグッズをたくさん購入してきた。ポスターはメトロの壁に貼ってあったと思しき大きなものが二枚、映画雑誌は束ねると十センチになるくらい冊数が多い。
さてさて、私がこの世におサラバしたあとは、これらの「お宝」はどこに行ってしまうのか。神保町で売ることになるのか、フィルムセンターがもらってくれるのか、今から心配している。