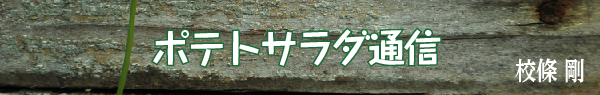ポテトサラダ通信 17
パパは何でも知っている
校條 剛
何でも知っているパパと、素敵なママと、長女ベティ、長男バド、末っ子キャシイ。(全員声を合わせて)「パパは何でも知っている!」
――というのが、アメリカのテレビ番組「パパは何でも知っている」の始まり方だった。いまでも、声が聞こえてくるほどに馴染んでしまっている。
このテレビドラマは30分だったから、コマーシャルを除くと実質は25分あるかどうかだったろう。その短い時間のなかで、いつもなにがしかの小さな出来事が起こり、多少の波乱があって、最後にパパが解決する。バドが何かトラブルを抱えた回だったと思う。集まった人々のまえでパパが演説めいた話をしたシーンをうっすらと憶えている。バドの行為には、理由があり、皆さんの寛容な心をもって、許してほしいというような内容だったのではなかろうか。そういうときのパパは自信に満ちているが、決して驕った素振りは見せず、ひたすら誠実な姿を見せる。パパの話の中身はすっかり忘れてしまっているが、そのとき受けた感動は心の深いところでまだ生きている。パパは別段大学の先生とかではなく、普通のサラリーマン、確か保険会社に勤めているという設定だった。
パパを演じていたのは、ロバート・ヤングという俳優で、ママは確かジェーン・ワイアットという女優さん。ほんとうの夫婦のように自然で、あるいは本当の夫婦以上にバランスのいいカップルに思えた。
この番組がいつまでも記憶に残っているのは、このエッセイの最初に紹介した〈何でも知っているパパと素敵なママ〉という毎回繰り返される導入部にあるのだが、それだけではなく少年の私に深い影響を与えた思想が流れていたからだと思う。
大げさに言うと、私に道徳とか倫理観というものを養わせてくれたのは、この「パパは何でも知っている」であり、その他、当時たくさん輸入されてテレビ放送されていたアメリカの現代ドラマや西部劇だったのだと思うのだ。極端に言うと、善なるもの、正義なるもの、さらに大きくいうと民主主義なるものを幼少期にアメリカのドラマから学んだのである。
その時代、1950年代から60年代、アメリカのドラマを見ていると、子供の背丈よりも大きい電気冷蔵庫や清潔なキッチンや食事室、くつろぎの場所である広いリビング、子供たち一人ずつに与えられた個室、自家用車も日常当たり前に使用するものとして登場していて、狭い畳の部屋の真ん中に据えられたちゃぶ台で食事して、氷の冷蔵庫を使っていた我々日本人の家庭にショックと憧れを与えたと言われる。多分そうなのだろうが、私の場合それは少しあいまいである。そういう物質的な事柄よりも、いま言ったような精神的な部分により影響を受けたのではなかったか。さらにかの地の人々のユーモアとウィットにあふれた会話にも強く惹かれたのだ。
アメリカは、フランスのような大人が中心の社会ではなく、家庭では子供が中心で、夫婦の描き方も子供が見てもいいように性的な表現を厳しく排除しているのもアメリカのテレビドラマの特徴だった。「パパは何でも知っている」などのドラマでは、夫婦が寝室を一つにしていることは見せても、決して同じベッドに同衾している姿などは見せなかった。セックスを予測させるシーンはアメリカのテレビでは基本的に排除されていた。
それでも、挨拶としての抱擁やキスはしょっちゅう描かれており、夫婦関係の彼我の違いに驚きを感じたものである。自分の両親がキスしている姿など想像したくもなかったが、テレビで見るアメリカの夫婦においてはごく自然に映った。
「パパは何でも知っている」のような家庭劇は、向こうではシチュエイション・コメディというらしく、これを短くして「シットコム」と表記することも多い。要するに登場人物が同じで、各回ごとに新たなストーリーは用意されているが、一つの「家庭」と「家族」というシチュエイションは同じという意味らしい。日本でのシットコムの最初は漫才の中田ダイマルが主役だった「スチャラカ社員」だそうで、この番組もよく観ていたのだから、私はシットコムが好きなタイプなのだろう。
「パパは何でも知っている」が教えてくれた道徳観とはけっして難しいものではない。しかし、「善」とは何か、「正義」は人が守るべき最高の道徳だと、具体例で示してくれたことは事実である。そして、私が観た、ほかの多くのアメリカ・テレビドラマも単純ながらテーマは「正義」の実現だったのではないだろうか。
だんだん話が広がって収拾がつかなくなると困るので、今回は、私がテレビで観ていたアメリカ製のドラマのタイトルをずらずらっと並べてみて、思いついたことを少し述べるだけにしたいと思う。私の同年代の読者の方々にも懐かしいタイトルがあるはずだ。
以下ではネットで調べたリストから、私がほとんど毎週観ていたタイトルのみを選んでみる。この時代、いかに西部劇が多かったかにもお気づきになると思う。
「ローン・レンジャー」「スーパーマン」「名犬リンチンチン」「パパは何でも知っている」「名犬ラッシー」「ちびっこギャング」「ブレーブ・イーグル」「テキサス決死隊」「ハイウェイ・パトロール」「シャイアン」「ガンスモーク」「ハイラム君乾杯!」「怪傑ゾロ」「コルト45」「マーベリック」「西部のパラディン」「幌馬車隊」「バット・マスターソン」「拳銃無宿」「ブロンコ」「ライフルマン」「うちのママは世界一」「タイトロープ」「アンタッチャブル」「わんぱくデニス」「ローハイド」「サーフサイド6」「パパ大好き」「ドクター・キルデア」「ベン・ケーシー」「ミスター・エド」「ギャラント・メン」「コンバット!」「バークにまかせろ」「ハニーにおまかせ」「それ行けスマート」「ザ・モンキーズ」……。
このネットからのリストで漏れている番組もまだまだあると思う。「アイバンホー」「ロビンフッドの冒険」「バイキング」「シュガーフット」や、タイトルは思い出せないが、大型扇風機のような動力で走る舟で湿地帯と縦横に走り、事件を解決するシリーズなんかも好きだった。ウォルト・ディズニーがホスト役をやる「ディズニー劇場(?)」もよく観ていた。
女性たちに人気があった「ララミー牧場」とか「逃亡者」とかは、何度かは観ているがどうにも人情を押し付けるようなえぐさが好きになれなかった。また、毎回のごとく観ていたが決して好きではないタイトルも混じっている。たとえば、「パパ大好き」がそれだ。
それにしても、こんなにたくさん、よく観ていたものだ。上記のお気に入りリストだけでも相当な数で、教育ママとして同級生の間で鳴り響いていた母親の目を盗んで、これだけの番組を観ていたことにいささか呆れてしまうことも事実だ。
現代ものとほぼ同数の西部劇に馴染んでいたことも特徴だろうか。西部劇においても描かれるのは「善と悪」の戦いであり、「正義」の実現であった。正義は常に勝利するという明快なテーマで貫かれた世界があったのだ。インディアンがまだ悪役の代表として描かれてはいたが、インディアンの酋長を主人公にした「ブレーブ・イーグル」のようなドラマも現われていて、変化の兆しは見えていた。西部劇であっても、というかむしろ単純な図式で成り立っている時代背景だからこそ、アクションを楽しむ一方で、現代劇よりもむしろ「正義」という形が明確だった。
「正義」と対立する、たとえば、「卑怯」という観念がある。まさに、現代では死語に近い言葉だが、私の少年時代には行動の規範として生きていたのは、「卑怯者になるな」という戒めだった。アメリカのテレビドラマでは、まともな人間は卑怯な行動は決してとらなかった。西部劇では、後ろから撃つというのが卑怯の代名詞だったので、そうした行為のために汚名を被った人物が寂しく生涯を終えたり、あるいは濡れ衣を晴らしてめでたしめでたしというような展開がよくあった。映画では「帰らざる河」や「真昼の決闘(ハイヌーン)」で、後ろから撃たねばならない状況もあることをラストで示していたのもやはり「卑怯」という「恥ずべき行ない」への道徳的な非難が強く存在していたからに他ならない。
赤胴鈴之助のセリフを借りると「卑怯者、名を、名を名乗れ!」というわけで、西部劇では、たいてい向き合って正々堂々と決闘するシーンが最後に用意されているのが普通だったのだ。
アメリカからの輸入作品が減ってからの自国製作の少年モノでもやはり「正義」の看板を振りかざす「おじさん」(「月光仮面」や「七色仮面」のおじさん)や「少年」(「少年ジェット」や「天馬天平」の少年)が主人公だった。現代の若者に「正義」の感覚が乏しく思えるのは、少年少女時代に観ていたアニメやドラマが、単純な正義を柱とした構造ではなくなっていて、バトルをするためにバトルをするというような「ゲームもの」か、恋愛もどきのドタバタを見せる「学園もの」ばかりになってしまい、背骨となる道徳感が備わっていないせいだとも考える。といって、文科省推薦の道徳ドラマなんて代物は見たくはない。
さてさて、卑怯の塊のようなテロリズムに覆われた現代では、ドラマづくりも難しくなった。こういう時代で育った子供たちは、どのような大人になるのだろう。