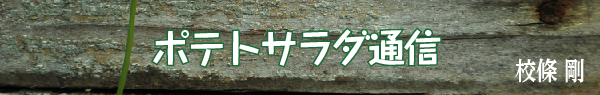ポテトサラダ通信 5
黒川博行さんと京都のママの話
校條 剛
黒川博行さんが直木賞を受賞したのは、最近嬉しかったニュースの一つでした。黒川さんは私よりも一歳上の昭和24年の早生まれ。満65歳。
黒川さんとの付き合いは古い。氏がサントリーミステリー大賞の佳作で文壇に登場して以来です。その佳作作品『二度のお別れ』が1983年の刊行だから、私が「会いたい」と連絡したことに応えて、新潮社に訪ねてみえたのが、その年のうちだとすると、知り合ってから30年以上になる計算です。初めてお会いしたときには、まだ高校の美術教師だったと思います。
黒川さんとの思い出は沢山あります。例えば、サントリーミステリー大賞の大賞受賞の夜。佳作では飽き足らず同賞に挑戦し続けた氏は、とうとう86年に『キャッツアイ転がった』で大賞を獲得します。この賞について、説明を加えると、お金は賞の名前にある通り、サントリーが出していたのですが、電通と文春が広告と出版を分け合って受け持っていました。選考会は公開で、若山弦蔵などの当時有名なナレーターに映像つきでストーリーを語らせるという派手な仕掛けが用意されていました。さらに、舞台の上の選考委員のほかに会場には読者選考委員が五十人ほど参加していて、大賞と同時に読者賞も投票される構成になってもいたのです。黒川さんの作品が読者賞も同時受賞だったかどうかは忘れてしまいました。
選考会のあとに授賞式が続きます。受賞式が終わると、パーティです。サントリーの主催ですから、酒の類はすべてサントリー製品であるのは当然でしょう。そのパーティも終わりがくると、主催あるいは協賛している出版社の編集者が受賞者を連れて、二次会の席を設けるのが普通です。ですがこの日、協賛の文春勢からはまったくそうした動きがなかったのです。お祭り好きな文春にしては珍しい不手際(?)だったと思います。
私は、その当時コンビを組んでいた単行本部門の佐藤誠一郎と二人で出席して、一連の流れを見ていました。黒川さんが、受賞者であるにも拘らず文春から誘いを受けていないのを知ると、黒川さんに声を掛けて、一緒に飲むことにしました。文春の賞を受けた作家を受賞の直後、新潮社が祝福したのです。実に不思議な夜でした。
直木賞に関して言えば、前回候補になったのが12年ほどまえで、それが五回目の候補でした。そのときも落ちて、多分一晩中、東京に出てくると必ず立ち寄る「ゼーロン」というバーの常連たちと麻雀で憂さ晴らしをしていたはずです。翌日、大阪に戻った黒川さんと私は偶然に出くわしています。そのエピソードは、今思い出すと笑えます。
私は29年在籍した月刊誌から新書の編集部に移った直後であったような気がします。新大阪止まりの新幹線から降りようと通路を歩いているときに、三人席を一人で占領して伸びている不埒者の姿が目に入りました。三人分の席を購入しているわけはないので、不埒者と私はそう思ったのです。しかし、興味本位で覗きこむと、明らかにその人物は、私の知り合いでした。前夜、直木賞を獲り損ねた黒川さんだったのです。「黒川さん、新大阪ですよ」と声をかけると、多少は睡眠がとれたのか、もぞもぞと起き上がります。私の顔を見ても驚きもしません。普通なら「あ、メンジョウさんか」とか言いそうなものですが、あくまでももぞもぞという動きだけ。疲労のため、言葉を失っていたのかもしれません。
その日の私の宿舎は、大阪に来ると定宿にしていた地下鉄御堂筋線の中津駅から地下通路で直結している東洋ホテル(今は廃業)でした。新大阪からわずか二駅です。
黒川さんの自宅は羽曳野というところですが、一度も行ったことがないし、どういう経路で辿りつくのかも知らないのですが、中津を途中に挟んでも遠回りではあるまいと黒川さんをホテルまで連れてきてしまいました。
地下のレストランで「昼から生ビール」を始めました。黒川さんは、「嫁はんに電話をしたい」と言って、店に入るまえに公衆電話から連絡をしていたはずです。恐らく当時はまだ皆が携帯電話を持っているということはなかったのでしょう。
私はもう文芸編集者ではありませんでしたし、黒川さんと京都や大阪で飲んでいた日々から時間が経っていて、付き合いの頻度が少なくなっていました。話題は途切れがちです。昨晩の経緯をまた蒸し返すほど私は無粋ではありません。生ビールを欲していたのは、私ばかりのようで、黒川さんのほうのジョッキは一向に減りません。それを見て私は、はっと気が付きました。このご御仁は、相当に疲れているぞ、と。あらためて顔の表情を確かめると、無表情なのです。喜びも悲しみもなく、無表情。疲労困憊。まっすぐに家に帰って、横にでもなりたいところを私が引っ張ってきてしまったのです。付き合いのいい黒川さんは、直木賞受賞作『破門』の二宮のように、イヤとは言えない性格のようです。真昼の宴会をすぐにお開きにしたことは言うまでもありません。
黒川さんと京都で一年に一回会っては、京都の飲み屋を巡っていた時期は正確には分かりませんが、サントリーミステリー大賞受賞後、すぐのことだったと思います。
当時、新潮社は、からすま京都ホテルを会場にして、新入社員の面接を行っていました。私と佐藤誠一郎と二人とも面接委員になっていたことを好都合に、二日目の面接が終了したあとに、黒川さんと待ち合わせて、黒川さんの知っているスナックを数軒巡る夜を過ごしていました。
黒川さんは、大阪育ちですが、大学は京都市立芸大だったので、学生時代から京都の町には馴染んでいます。今、私が勤務している京都造形芸術大学の副学長 大野木さんとは同じ彫刻科の同級生だというのですから、縁というのは不思議なものです。
黒川さんは友人に紹介されたという「チャム」というスナック(今でもスナックというのだろうか。簡単に言えば、バーである)に我々を連れて行き、その後、そのスナックが夜の京都の中継所になります。チャムがあったのは、四条大橋を祇園のほう、つまり東に渡り、二本目の大和大路通りという、地元の人にはともかく、観光客には馴染みのない地味な通り沿いにあるビルの二階にありました。知る人しか知らない、知らない人は一生知らないという立地です。この時点で既に集客に難があることが想像できるでしょう。あとで分かったのですが、経営はなかなか苦しかったのです。
チャムから始まって、もう二軒くらいカラオケのできるスナックをハシゴします。当時はカラオケボックスなるものは存在せず、スナックでマイクを握って、モニターの伴奏に合わせて歌ったものです。黒川さんはやはり一番うまかったですね。酒、麻雀、カラオケと、オンナ以外は好きこそものの上手なれの見本という感じでした。
さて突然ですが、ここから、黒川さんの話題から、チャムのママの話に移らせてもらいます。
チャムのママは佐賀県小城郡小城町出身のすらっとした四十歳代の女性でした。顔はいつもむくんだように膨らんでいましたが、女優の三ツ矢歌子に似ていると言えばだいたいの雰囲気が分かるでしょうか。両脚が形よく伸びていて、パンタロンスタイルがよく似合っていました。名前は吉田眞佐子。色気があるよりもないほうで、気持ちが明るいよりも暗いほう、よく喋るよりも寡黙なほうで、水商売にそもそも向いていたのかどうか。聞きかじりなのか、小説にも興味があるようで、そこが黒川さんや私が馴染みやすかった点だったのでしょう。聞くと、産みの母に幼いころに捨てられて、オバさんの家で育ったらしい。寂しい幼年期、思春期を過ごした人でした。十代で家を出て、水商売の世界に入ったあとはいろいろあったらしいのですが、苦労のほうが半分以上であったことは口ぶりで分かりました。
ある年の瀬が迫っているもう少しで仕事納めという頃合いだったでしょうか、東京にいる私のデスクの電話が鳴って、チャムのママでした。急いた口調で、お金を用立ててほしいと言います。二十万円至急必要だが準備がないので、一時的に貸してほしいと言うのです。切羽詰まっていて、今日明日に入金してほしいのだと。私は編集長になっていたころだと思います。それでも「うぶ」だった私は、商売をしているとそんなこともあるだろうと、すぐにお金を振り込む約束をして、すぐに銀行に走ったのだと思います。断わっておきますが、男女の関係は一切ありませんでした。
のちに、女性から突然お金を貸してほしい、必ず返すからと言われても、そのお金は上げると解釈したほうがいいことを勉強することになるのですが、その当時はまだまだ人がよかったのです。
翌年、私は毎月一万でもいいから返すようにと彼女に伝えたのですが、とうとう一銭も返ってきませんでした。それもそのはず、彼女はたいへん高額の借金を背負っていたのです。
一年くらいが過ぎて、三月のお彼岸のころだったと思います。私は部下と単行本編集者の三人で、西村京太郎さんの取材で丹後方面を回り、京都駅に戻ってきました。一人で帰れるからという京太郎さんの言葉に甘えて、新幹線車両から先生を見送り、京都には足跡を印さずに帰京してしまいました。あとで知ったのですが、その前夜遅く、チャムのママ、吉田眞佐子は帰宅のタクシーのなかで、急激に襲ってきた脳溢血のためにあえなく亡くなっていたのです。
眞佐子ママの死を知ったのは、一か月くらいあとでした。会社に電話がきたのです。チャムで働いていた女性からで、店が終わって帰宅するタクシーで亡くなったこと、お葬式の騒動のこと、借金取りのことなど詳しく話してくれました。借金が2000万円もあったため、葬式のお金がなく「福祉」でしてもらったこと。故郷から、おばさん(養母のおばさんではない)が喪主になったが、借金取りを恐れて、遺骨と位牌だけ持ち、佐賀に逃げ帰ったこと。自分たち従業員からもお金を借りていたこと。
「多分、あなた様もお金を貸したことがあるのではないかと、ご連絡してみたのです」
彼女は、佐賀県のおばさんの住所と電話を教えてくれました。私は、おばさんの家に行って、そして墓参りをしようと思いました。それには理由があります。
当時、佐賀県には作家の笹沢左保氏が、東京を離れて暮らしていたのです。最初いた古湯温泉から佐賀市に居を移していたころだと思います。私はすでに何度か佐賀を訪れていて、小城町がどのあたりにあるのか知っていました。JR佐賀駅からタクシーでさほどの距離ではありません。
実際、それから程なくして、また出張で佐賀市に出かけ、そのついでに眞佐子さんのおばさんの家を訪ねることができました。それなりに立派な構えの家の玄関を入ると、田舎のトイレの臭いが鼻を突きます。仏壇に眞佐子さんの位牌を置いているというので、まずは位牌に手を合わせようと膝を進めました。その位牌が衝撃でした。紙なのです。多分、本体は木製なのでしょう。本体に重ねた厚紙は、無造作に巻かれてあって、端がめくれています。戒名を記した文字も乱暴に書かれている感じで、一目見た印象ははなはだ荒んでいました。これが福祉というものか、京都の差別思想というものか、と暗然とした気持ちになりました。多分、東京では「福祉」といえども、もう少しましな位牌を手配してくれたのではないでしょうか。
トイレの臭いに閉口した私は、おばさんとの話題にも事欠いていたので、すぐにお墓の場所を尋ねました。お墓は、田んぼのなかの一段高くなった墓地の一角に建っていました。石を磨き直したのか、黒御影の表面が明るい陽射しのなかで光沢を見せています。私は、町に着いたときに買い求めた花を供えてから、屈みこんで暫く手を合わせました。
周辺は田んぼや畑ですから、見回すと作業に勤しんでいるお百姓たちの姿がぽつんぽつんと目に入ります。眞佐子さんが話していた言葉を思い出しました。「里帰りするとね、道で同級生の男の子に会ったりするのよ。元気かぁ、なんて声を掛けられる。そんなとき、ああ、こういう人と結婚して、ここに住んでいればよかったと、すごく後悔することがあるんよ」
その後、電話をくれた従業員の女性に京都で会いました。彼女の話によると、眞佐子さんの実母は、なんと東京の世田谷区で元気に暮らしているということでした。育て親であるおばさんは、眞佐子さんが京都に引き取って面倒を見ていたのですが、眞佐子さんが亡くなるふた月ほどまえに大往生を遂げていたことも分かりました。眞佐子さんは、養母のあとを追うように足早に去っていってしまったのです。
我々のような酒場に入り浸っていたような編集者は、酒場の女性たちの人生に図らずもずぶずぶと入っていってしまうことがあります。少なくとも、私が知っている酒場のママたちの晩年は決して幸せなものではなかったような気がします。そのせいではないでしょうが、この頃私は、まったく酒場には行かなくなりました。