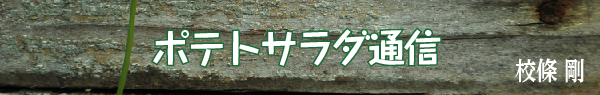ポテトサラダ通信 4
水丸さん逝く
校條 剛
安西水丸さんが亡くなったと聞いたのは、京都駅に向かう5番のバスに乗り込んだ直後だった。このところ、京都を往復することが多い。2014年春から京都造形芸術大学の文芸表現学科の教授として採用されたからだ。
京都には、水丸さんもどこかの専門学校で教えるために定期的に来ていたはずだ。もっとも、二十年以上もまえのことだ。
最初に水丸さんを紹介してくれたのは、高輪に本社がある精美堂という版元製作会社の営業マン永峰勝美さんで、彼からは安久利徳さんも紹介してもらった。私は小説雑誌の編集者だったから、挿絵を画いてくれる新しいイラストレーターを常に探していた。永峰さんがどこでこの二人と知り合ったのかは、分からないがまったく無名だった二人が後にこの世界の大御所になるのだから、彼の目は確かだった。
水丸さんは当時、まだ潰れるまえの平凡社に勤めていたので、初めての出会いは、威圧するような堂々たるファサードが特徴の平凡社社屋でだった。
安西水丸は、もちろん本名ではなく、安西はご母堂の実家の姓で、水丸は会社の同僚・嵐山光三郎さんの命名だった。安西家は、東京ガスではなく、古河電工だったか、有名な財界人につながる名家だったと記憶する。
水丸氏は、幼いころ病弱だったので、房総の千倉にある別荘で母親や姉たち、使用人たちに囲まれて育ったのだ。東京の家は赤坂だし、父親が早死にしたほかは、経済的にはなんの不安もなく育った。長じてからも、お金は自然とついてまわり、生涯金銭的な心配とは無縁だった。
脱線したが、平凡社の受付では、渡辺昇さんを呼んでもらった。それが安西さんの本名だったのだ。
磨かれた大理石の平凡社の廊下を背中を丸めて、なんだか頼りない足取りで表われた水丸さんは、赤っぽいチェックのシャツに、お腹周りに余裕のある、ちょっとダブダブ感のあるジーンズという姿で現われた記憶がある。この会社の自由な雰囲気が、威圧的な社屋と合っていない気がした。ロビーで打ち合わせをしているときに、本名・祐乗坊英昭、ペンネーム嵐山光三郎そのひとが通りかかり、私を紹介してくれた。のちに嵐山さんの小説原稿を何度も貰ったり、『追悼の達人』という傑作連載をしてもらうことになるとはそのときには想像もできなかった。
水丸さんは、田中小実昌の作品が好きなんだと言う。コミさんの存在感そのものが気に入っているようだった。そこでコミさんの小説の挿絵を二回ほどやってもらってから、こんどは新しく連載を始めることになった「ぼくのシネマグラフィティ」という映画エッセイのカットをやってもらうことになり、二人を引き合わせるために、新宿ゴールデン街で三人で飲んだ。水丸さんが、平凡社を辞めるまえかあとか分からない。
しかし、テレ屋の二人が打ち解けることはなく、私を真ん中に挟んだままクールに時間が過ぎたような気がする。コミさんは、案外趣味が強かったから、水丸さんの絵を気に入らなかったのかもしれない。コミさんの奥さんは、画家の野見山暁治氏の妹だったから、コミさんは野見山さんみたいな絵が好きだったのではないだろうか。水丸さんの「ヘタウマ」絵なんていうジャンルには案外関心が届かなかったのだろう。
それから随分と後のことだが、半村良氏に浅草案内のような読物を連載してもらうときに、担当者で編集長だった横山正治の指名で水丸さんに絵を頼んだことがあった。半村、安西、横山、校條の四人で連載開始の景気づけに浅草の半村氏行きつけの店を何軒か回った。そこでも、半村さんと水丸さんが打ち解ける雰囲気がなかった。あろうことか、この時には、酔っ払った半村さんが、編集長の横山の頭をポコポコ叩きだして、おかしな雰囲気になってしまった。やはり、水丸さんと気が合う作家は、嵐山さんであり、村上春樹さんであるということなんだろう。
酒に関してのエピソードではこういうことがあった。水丸さんというより、私の失敗談である。
水丸さんの個展が六本木飯倉交差点近くの広い画廊で催されたときのことである。まだ、私も三十歳くらいのころで、水丸さんも会社を辞めて独立した直後ではないだろうか。個展のオープニングの日には、アルコールと軽食が用意されて、招待された関係者で乾杯するのが習わしである。この日は、日本酒の一斗樽が用意されていて、鏡割りのあと配られた升で薫り高い清酒を味わうことになった。私は、そもそも酒に強くもないのに、すきっ腹には耐えられない性質で、空腹を埋めるためだろうか勢いよくぐびぐびと飲んでしまうことが多かった。まして、その日はビールではなく、いきなり日本酒。気分よく喉に流し込んでいるうちに、わけが分からなくなった。意識が飛んで、時間と空間の制約から逃れて別世界に飛んでいったのである。
気が付いたときには、どこかソファのようなところに仰向けになっていて、視線の先には天井が見えた。会場を埋めていた客たちのざわめきはもうなかったのは、当たり前で、催しはとっくに終わっていたのだ。水丸氏ももう別の酒場に移動したのか、影もなかった。画廊の関係者だけが残って私が目を覚ますのを待っていたらしい。慌てて会場を後にした。
後日、ことの真相が明らかになった。といっても、ひどく酔ったあげく、何かに躓いて後ろにひっくり返ったらしい。そのままお寝んねだったと。怪我をしている様子もなかったので放っておかれたらしい。
会場には知り合いのイラストの方々が何人もいたが、そのうちの一人、峰岸達氏から酔態をからかわれた。あんな酔い方は恥ずかしいというようなことを言われたのだ。まあ、まっとうなご意見ですね。そのあと、水丸氏に「先夜は見苦しいところをお見せして済みません」と謝ったのだ。それに答えて、水丸さんが言ってくれたセリフは行を変えてお見せしたいと思う。
「編集者なら、あのぐらい飲まなくちゃダメですよ」
この言葉で一気に気持ちが軽くなった。嬉しかった。
朝日新聞の死去報告の記事では、小説の代表作に『アマリリス』を選んでいる。これは、水丸さんの初めての小説集だったのではないか。そして、この作品は私が担当したものである。水丸氏の手書きの文字は、書き順が違っているせいか例えば、ジとヅの文字が同じに見えてしまったりしていた。私には覚えがなかったのだが、そういう書き癖や文章に対して、まるで「バカじゃないの」みたいな指摘の仕方をしたらしくて、あとで控えめに抗議されたこともあった。私は自慢ではないが、なかなかに傲慢な編集者だった。横山のこと、笑っていられないよね。
それでも、水丸さんと二人で飲むのは楽しかった。感性のいちいちがこちらの気持ちに染み透ってくるというのか、映画の話をしても意見が対立することがまったくなく、いつも盛り上がった。
水丸さんはかなりの映画ファンで、そういう人にありがちな傾向だが、自分の好みの映画をほかの人間にも見せたがった。私は、水丸さんがわざわざ手持ちのヴィデオからダビングしてくれたテープを貰ったこともある。確か小津作品の「東京暮色」が入っていたのではないか。私の大好きな有馬稲子が出る映画だが、有馬も自殺する役だし、全体的に小津作品として異例に暗い作品だったが、のちのちまで記憶に残る作品だ。レーザーディスクを一枚もらったこともある。水丸さんがかなり気に入った映画だったのだろう。タイトルは「バグダット・カフェ」である。実は、もらってから三十年くらい経つが、とうとう最後まで観たことがない。最初からどうしても乗れなかったのだ。水丸さん、ごめんなさい。いつか絶対に観ておきます。
映画と言えば、こういうこともあった。ソ連時代の名画でチェホフ原作「子犬を連れた奥さん」というヘイフェッツ監督の作品がある。テレビで何度か放送していたし、DVDも発売されているので、観た方も多いのではないだろうか。映像がシャープで、ヤルタやモスクワや名も知らない地方都市の雰囲気が濃厚に再現されていて、なによりも音楽がすごくよくて、音楽を聴くためだけにときどき好きなシーンを観ることもある作品だ。
この映画の主人公の役者が、水丸さんとよく似ているのだ。顔立ちとか、身体の動きが似ている。つまり、全体として似ていると私は感じたので、水丸さんに是非ご覧くださいとお伝えした。ある晩、テレビで放送があり、奥さんと二人で観たらしい。しかし、その後、感想を聞いても、はかばかしい返事はなかった。本人は似ているとは感じなかったのは確かだが、他の皆さんの意見も聞きたいところだ。
実は水丸さんとは、ここ十年以上一緒に飲んだことがない。それどころか、顔を合わせたのも、多分、毛利彰さんの追悼展が銀座で開かれた三年ほどまえに、イラストレーター団体の会長として水丸氏が挨拶をしたときが最後になるだろう。
一度、一度と思っているうちに突然の訃報を聞くことになった。父親、兄と早く亡くしていて、家系的に短命だったこと、酒好きで毎日のごとく飲んでいたことなどが、逝去を早めたのかもしれないが、たった71歳ですよ。もったいなさすぎる。